すららはうざい!?すららが選ばれるおすすめのポイントを紹介します
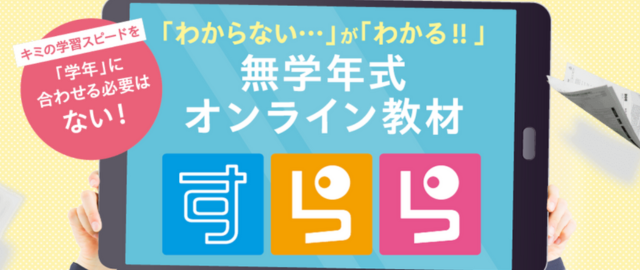
「すららはうざい」と感じる声がある一方で、「すららが良い!」と選ばれている家庭が非常に多いのも事実です。
特に、不登校や発達障害の子どもを抱える家庭では、「子どもが自分のペースで学べる」「親が無理に教えなくていい」「サポート体制が厚くて安心」という声が多く見られます。
すららは単なるタブレット教材ではなく、プロのコーチによる個別サポートや、AIによる理解度チェック、アニメーションによる対話型授業など、多角的なアプローチで子どものやる気を引き出してくれます。
その結果、長期的に継続しやすく、苦手な教科も克服できる設計になっているのです。
つまり、「うざい=丁寧すぎるサポート」と捉えると、むしろ家庭学習の強い味方であることがわかります。
すららのおすすめポイントをまとめました
「すららって、なんかうざいって聞いたけど…」と不安に思っている方、実はその“うざい”の正体は「サポートが手厚すぎる」からなんです。
すららは、ただのタブレット学習ではなく、コーチによる個別サポートやAIによるつまずき分析、さらにアニメーションによる楽しい授業など、サポートが盛りだくさん。
それを「干渉されすぎ」と感じる子どももいれば、「ありがたい」と感じる家庭もあるというわけです。
とはいえ、そうした“熱心すぎる”支援の裏には、「継続して学べるように」「親の負担を減らすように」といった、明確な意図があります。
だからこそ、発達障害や不登校の子どもを持つ家庭からは「助かった」「他の教材では続かなかったけど、すららは続けられた」と支持されているんです。
つまり、うざい=それだけ丁寧ということなんですね。
| ポイント | 具体例 |
| 無学年式 | 小1の子が中学英語も学べる!苦手もじっくり戻れる |
| 対話型授業 | アニメキャラとの対話形式で「双方向」学習 |
| すららコーチ | 親がスケジュール管理しなくてOK!丸投げ可能 |
| 発達障害・不登校対応 | AIがつまずきを解析→無理なく学習再開できる |
| 成果が見える | テスト・レポート・定着診断で、親も安心 |
| 英語3技能対応 | 話す・聞く・読むがまんべんなく学べる |
| 兄弟OK | 1契約で複数人OK→家族で使えば超コスパがいい |
ポイント1・無学年式!学年に縛られず、得意も苦手も自由に学べる
すらら最大の魅力の一つが「無学年式」であること。
学校のように「学年で区切られた進度」に縛られることがないため、今の子どもの理解度や得意・苦手に合わせた学習ができます。
たとえば算数が苦手な小4の子が小1レベルからやり直すのもOK。
逆に、得意な英語は中学生範囲までどんどん先取りできるのも大きなメリットです。
「わからないまま進む」「退屈だからやる気が出ない」といった悩みを解消し、ストレスなく“自分だけの学習ルート”を歩めるのが、すららの無学年式。
特に、発達に特性のある子や、不登校の子にもフィットしやすい設計です。
学力や進度に関係なく、自分のペースで学べる
学年や年齢ではなく「本人の理解度」に応じた学習を進められるのが、すららの無学年式最大の特徴です。
苦手単元でつまずいても、学年をさかのぼって自分に合ったレベルから復習できます。
逆に、得意な科目はどんどん先に進められるから、子どもの“できる!”が積み重なり、勉強に前向きになれるきっかけになります。
固定されたカリキュラムに縛られることなく、自分のリズムと興味で学習できるため、ストレスが減り、継続しやすくなるのも嬉しいポイント。
特に学習障害や不登校など、学校のペースが合わない子どもにも最適です。
「得意はどんどん進める」「苦手はじっくり戻る」が簡単にできる
多くの子どもが持つ「苦手は飛ばしたい」「得意は先取りしたい」という本音。
すららではそれが許されます。
AIが苦手を診断し、戻るべき単元を自動提案してくれるだけでなく、得意な単元はどんどん進めてOK。
固定されたスケジュールがないから、本人のやる気次第で「楽しい」「進んでいる」という成功体験が積みやすくなります。
親が「この単元もう1回やった方がいいんじゃ…?」と不安にならなくても、すらら側がちゃんと案内してくれるから安心。
子どもの“わかる”に合わせて柔軟に学習できるから、ストレスを感じずに取り組みやすいんです。
ポイント2・「対話型アニメーション授業」で、わかりやすい&飽きない
すららの授業は、一般的な「ただの解説動画」とは違います。
キャラクターと対話しながら進める“インタラクティブ形式”になっており、子どもが「受け身」にならずに学べるのが特徴。
イラスト・アニメ・図解などが豊富に盛り込まれていて、特に視覚優位な子にはぴったりの設計です。
また、正解すればその場で褒めてもらえる仕組みになっており、自己肯定感が高まりやすいのもポイント。
「やりなさい」と言わずとも、「次のステージに行きたい!」と自然にやる気になる声が多く、学習が“遊び感覚”に変わる子も少なくありません。
アニメキャラが「先生役」として、子どもと会話しながら進めてくれる
「いきなり問題だけ出されると緊張してしまう」「教科書の説明が難しくて頭に入ってこない」。
そんな子どもにも安心なのが、すららの対話型アニメーション授業。
キャラクターたちが「○○ちゃん、これはどう思う?」と優しく語りかけてくれるので、まるで家庭教師と対話しているような感覚になります。
言葉がけやテンポも調整されており、子どもが置いてけぼりになることなく、学習が進んでいくんです。
選択式で答えるスタイルなので、文字入力が苦手な子でも気軽に取り組めます。
難しいことも「図や動き」で視覚的に理解できる
すららは文字だけの説明ではなく、図解やアニメーションを活用して、抽象的な内容も視覚的に伝えてくれます。
特に算数や理科の単元で、図形の動きや時間の流れなど「イメージしにくい」内容が出てきた時には、紙の教材より圧倒的に理解しやすい設計。
感覚的に理解しながら進められるため、言葉だけの解説に抵抗がある子や、読解に苦手意識のある子でも「なるほど!」という納得感が得られやすいです。
キャラが褒めてくれるからやる気UP!飽きっぽい子でも続きやすい
正解すると「すごいね!」「その調子!」とキャラクターが褒めてくれるのも、すららの魅力の一つ。
褒められることで「もっとやりたい」「次も頑張ろう」という気持ちが自然と湧いてくるんです。
ポイントがたまる演出や、レベルアップする画面など、“ゲーム感覚”で学べる要素も満載。
集中力が短い子や、勉強が嫌いな子でも、継続して取り組みやすい仕組みが整っています。
ポイント3・「すららコーチ」がついて親の負担が激減
子どもに学習させるのは、教材よりも「親の気力」が必要。
そう感じている方にこそ知ってほしいのが、すららの“コーチ制度”です。
プロの「すららコーチ」が、子どもの特性・ペース・理解度に合わせて学習計画を提案し、毎週の学習状況に合わせてフォローしてくれます。
親は毎日ガミガミ言う必要なし。
質問やつまずきは直接コーチに相談できるので、子どもも安心して続けられます。
しかも、親にも定期的に報告が届くから、進捗が見えて「ちゃんとやってる」と実感しやすいのも嬉しいところ。
忙しい家庭ほど、コーチ制度のありがたさを実感できるはず。
プロの「すららコーチ」が学習計画を作成&フォローしてくれる
子どもに合った学習計画を、自動ではなく“人間のプロ”が組んでくれる。
それが、すららのコーチ制度の信頼ポイントです。
AIだけでは判断できない「家庭の事情」「性格」「集中力」なども考慮して、一人ひとりにぴったりなプランを提案。
進捗に応じて調整してくれるので、無理なく、無駄なく学習が続けられます。
塾講師経験者や教育の専門知識を持つ人が対応してくれるので、安心感も抜群です。
子どもの特性や希望に合わせたオーダーメイド学習計画を立ててくれる
「学校の授業はついていけないけど、英語は好き」「反復が得意だけど応用が苦手」など、子どもの学習特性は様々。
すららコーチはそうした一人ひとりの個性に合わせた学習スケジュールを作ってくれます。
週ごとの到達目標、日々の進め方、つまずきやすいポイントの対応方法など、親も驚くほどきめ細かいアドバイスがもらえるのも特徴。
家庭学習を“放置しないで見守る”スタイルが実現します。
質問や相談はコーチに直接できるから親は見守るだけでOK
「なんでこの問題わからないの?」「もっとやらないとダメでしょ」そんな言葉がつい出てしまうご家庭にこそ、コーチ制度はおすすめ。
学習の進め方、質問への回答、やる気が出ない時の対処法など、すべてコーチがフォローしてくれるので、親は口を出さずとも安心して任せられます。
感情的にならず、プロ目線で声かけしてくれる存在がいることで、子どもとの関係性も穏やかに保てるのです。
ポイント4・発達障害・不登校にも対応!学習への不安を取り除いてくれる
すららは「文部科学大臣賞」を受賞した実績もある、信頼度の高い家庭学習教材です。
最大の特長は、発達障害や不登校の子どもにも対応した柔軟な設計にあります。
ADHD・ASD・LD(学習障害)など、発達に特性がある子にとっては「自分のペースで学べる」「間違えても怒られない」「褒められる」などの安心材料が揃っています。
また、不登校の子に対しても“学校の代わり”ではなく、“子ども本人の意思で学びを継続できる環境”として活用されるケースが増えています。
AIがつまづきの原因を特定し、個別に問題を出してくれるから、わからないまま先に進まず、成功体験を重ねることができます。
「できた!」が日常になることで、勉強に対する恐怖や拒否反応が少しずつ減っていく──そんな変化を、親子で実感できるのがすららです。
文部科学大臣賞も受賞している学習支援ツール
すららはただのタブレット教材ではなく、文部科学大臣賞を受賞した経歴を持つ「教育支援ツール」です。
特に、不登校・発達障害の子どもたちへの支援実績が評価され、全国の自治体・教育委員会からも注目されています。
子どもたちが安心して学びを継続できるよう、教材の内容だけでなく、設計思想そのものが「誰ひとり取り残さない」ことを大切にしているのがポイント。
家庭だけでの学習に不安があるご家庭でも、安心して導入しやすい信頼のある教材です。
発達障害(ADHD、学習障害など)の子にも適した設計で安心
ADHDの子には「集中力の続く10~15分」のスモールステップ構成。
LD(学習障害)の子には「視覚・聴覚の多感覚」アプローチ。
ASDの子には「決まった手順」や「予測可能な設計」が安心材料になります。
すららは、こうした多様な学び方にフィットする設計がされているため、特別支援の現場でも使用されることがあります。
学習で「つまずいた経験」が多い子でも、否定されず、じっくり取り組める設計なので、自信を取り戻すきっかけになることも。
不登校で学校の授業に追いつけない子でも取り組みやすい
すららは不登校の子どもでも無理なく始められる教材です。
「学校に行けていない」という焦りやプレッシャーを感じることなく、自宅で自分のペースで進めることができます。
さらに、すららを使った学習は「出席扱い」として認められるケースもあり、内申点や進学への影響を抑えることも可能です。
学校の授業をなぞるのではなく、子どもの「今の理解度」からスタートできる点が、不登校の子にフィットする大きな理由です。
つまづきをAIが解析→理解不足の箇所を自動で出題してくれる
学習中に「わからない」「間違えた」が出たときに、ただ正解を見せるだけでは意味がありません。
すららは、AIが子どもの解答履歴を分析し、どこで理解が止まっているのかを明確に特定してくれます。
そして、そのつまづきポイントに戻って解説→再確認問題を出題してくれるので、穴を埋めながら理解を進めることが可能。
復習のタイミングも自動なので、子どもが“置き去り”になる心配がなく、親も安心です。
ポイント5・オンラインテスト&リアルタイム学力分析で、成果が見える
すららは学習して終わり、ではありません。
オンラインでの「ミニテスト」や「確認問題」を通じて、定着度をその場でチェック。
さらに、AIが分析した学力状況をもとに、次にやるべき単元が明確になります。
保護者には、学習レポートが定期的に配信されるため「何をどこまでやったのか」「どの教科が苦手なのか」が一目でわかります。
成績アップという目に見える成果だけでなく、「どこまで理解しているか」という学力の“中身”が見えるから、子どもの今の学習状況に応じて適切なフォローが可能に。
結果を“見える化”することで、親の不安も軽減されます。
小テストで間違えた問題を即フィードバックできる
「その場で理解できたかどうか」が学習定着に大きく影響するのは言うまでもありません。
すららでは、1ユニットごとに確認問題や小テストが用意されており、間違えた問題には即座にフィードバックが届きます。
ただ正解・不正解を伝えるだけでなく、なぜその答えになるのかを丁寧に解説。
再チャレンジもできるため、理解が深まりやすいです。
つまずきを放置しないから、親が後から不安になる必要もなし!
定着度診断でAIがどこが苦手か把握し即対策問題を出してくれる
学習が進んでいるように見えても、実は理解が浅い──そんな事態を防ぐのが「定着度診断」です。
すららのAIが「理解済み」「苦手」「要復習」などを細かく分類し、個別に対策問題を自動で出題してくれます。
単元ごとの到達度が見えるから、子ども自身も「どこが苦手なのか」「あとどれくらいやればいいのか」が明確になり、モチベーションアップにつながります。
保護者にもレポート配信し「何をどこまで理解しているのか」をしっかり確認できる
すららでは保護者向けの「学習レポート」がメールなどで定期的に届きます。
「今週は英語を○○分学習」「数学の○○単元を終了」など、詳細な学習履歴と到達度が見えるから、子どもに「今日なにやったの?」と聞かなくても把握可能。
特に中学生以降、親が勉強内容に口を出しづらくなる時期には、この機能が大活躍します。
レポートを見ながら「よく頑張ってるね」と声をかけるだけで、親子関係もいい雰囲気に◎
ポイント6・英語が「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能対応
すららの英語は、ただの文法暗記ではありません。
「リスニング・リーディング・スピーキング」の3技能にしっかり対応しています。
小学生から中学生、高校生まで幅広く使える設計で、特に英語初心者にとっては“耳から慣れる”ことができる点が大きな魅力。
リスニングではネイティブの音声が使われており、自然な発音に耳を慣らすことができます。
さらに、音読練習ではAIが発音をチェックしてくれるので、「正しく話す」力も身につきやすいんです。
単語や文法の解説もアニメーションや図解で進むため、視覚的にも理解しやすく、英語が苦手な子どもでも取り組みやすい設計になっています。
英検対策にも活用できるレベルなので、将来に向けて英語をしっかり身につけたい方にはぴったりですよ。
ネイティブ音声のリスニングを学ぶことができる
すららの英語コンテンツでは、全編を通して「ネイティブ音声」が使用されています。
いわゆる“機械音声”ではなく、生きた英語のリズムや発音を体感できるのがポイント。
小学生のうちからネイティブの発音を耳に入れておくことで、自然とリスニング力がアップします。
特に、英語の「音とスペルの一致感覚」が育ちやすく、フォニックスにも通じる基礎が身につきます。
音読チェックでスピーキング練習ができる
すららには、音声を真似して発話する「音読チェック機能」が搭載されています。
発話内容をAIが認識し、正しく話せているかどうかを評価してくれる仕組みです。
間違えてもやり直しができるので、スピーキングの練習を“安心して何度でも”行えるのが魅力。
恥ずかしがり屋の子でも自宅なら声を出しやすく、英会話スクールに通わずとも口頭練習ができるのは心強いですよ。
単語・文法もアニメーションで丁寧に解説してくれるから英検対策におすすめ
すららの英語は「単語・文法」もしっかりカバーしており、その解説がとてもわかりやすいんです。
アニメーションと音声を組み合わせて、視覚・聴覚から同時に理解できるので、暗記が苦手な子でもスッと頭に入ってきます。
中学英語の基本から高校入試レベルまで対応しているため、英検3級〜準2級の対策にも活用できます。
特に文法のロジックが苦手な子にこそ、ぴったりの教材です。
ポイント7・料金体系が「1人分じゃない!」兄弟OK&科目追加自由
すららは、契約者1人分の料金で「兄弟も一緒に使える」という珍しいシステムを採用しています。
通常、タブレット教材では1人1契約が基本ですが、すららは1契約で複数人のアカウント登録が可能。
たとえば、小学生の兄と中学生の妹が同じ契約で使うと、追加費用なしで家庭の学習コストを大きく削減できます。
また、科目ごとの追加・削除も自由なので、「国語だけやりたい」「英語を後から追加したい」などのニーズにも柔軟に対応できるのが魅力。
教材の内容も兄弟別にカスタマイズ可能だから、無理なく、それぞれの子に合った学習ができるんです。
家族全体の教育費を抑えつつ、効果的な学習が可能な「コスパ最強教材」として支持されている理由がここにあります。
1つの契約で兄弟同時利用OK!(人数分の追加料金なし)
すららは「1契約=1人」ではありません。
なんと1つの契約で兄弟・姉妹の利用が可能なんです!人数分の追加料金が不要なので、2人以上の子どもがいる家庭にとっては大きな節約になります。
それぞれの学習履歴や進捗は別々に管理されるので、学年が違っても安心して利用可能。
兄弟でお得に使える教材を探しているなら、すららは間違いなく有力候補です。
小学生の兄と中学生の妹、同じ契約内で利用できるからコスパがいい
兄弟で年齢や学年が違っても、同じ契約内で利用できるのがすららの強み。
たとえば小学生の兄が算数、中学生の妹が英語と理科、というように、必要な教科をそれぞれ自由に選んで学習できる仕組みになっています。
1人ひとりに合わせた学習を、それぞれの画面・進捗で管理できるから安心。
しかも、追加料金はゼロ。
これ、思ってる以上にコスパ最強です。
科目ごとに選んで追加できるから、無駄がない
すららの料金体系はとってもシンプル。
3教科・4教科・5教科と選べるだけでなく、「途中で追加したい」「今は国・算だけでいい」という柔軟な運用も可能です。
子どもの成長に合わせて教科を増減できるから、「最初から全部入ってるけど使わない教科がある」といった無駄が出ません。
必要な分だけ払うスタイルなので、家計にもやさしく、長く続けやすいのが魅力です。
【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材にはないすららのメリットについて
「すらら」は“うざい”という声がある一方で、実は他の家庭用タブレット教材にはない優れたメリットがいくつもあります。
その代表が「対人サポート」と「発達障害・不登校への対応力」。
さらに「無学年学習」で学力差にも柔軟に対応できる点も見逃せません。
これは、ただのオンライン教材ではなく、“子ども一人ひとりの背景”に寄り添う教育支援ツールと言えるでしょう。
特に、すららコーチによる個別対応は、親の負担を大きく軽減し、子どもの学習を伴走型で支えてくれる大きな安心材料です。
不登校支援や発達障害に特化した実績もあり、「学校が合わなかった」「ついていけなかった」と感じていた子どもたちにも新たな希望を与える存在です。
うざいどころか、きちんと使えば“心強い味方”になりますよ。
メリット1・対人サポート付き!「すららコーチ」がある
すらら最大の魅力は、AIだけに頼らない「人のサポート」がついていること。
すららコーチと呼ばれる専門スタッフが、子どもの学習進捗を丁寧に見守り、必要なタイミングで的確なアドバイスや声かけをしてくれます。
オンライン学習でありながら、“完全な放置”にならないのが安心ポイント。
コーチがいることで、保護者が毎回進捗をチェックする必要がなくなり、親の負担も大きく軽減されます。
また、子どもにとっても「応援してくれる大人がいる」という安心感がモチベーションにつながるのです。
教材だけを渡されて終わり…というよくあるタブレット教材とは一線を画しており、学び続けるための「仕組み」が整っています。
すららはプロの学習コーチが進捗を管理してくれる
すららコーチは、単に教材を見守るだけではありません。
子ども一人ひとりの特性や学力レベル、目標に応じた「進捗管理」をしっかり行ってくれます。
「今日はここをやるといいよ」「苦手がここにあるね」など、具体的な声かけをメールでしてくれるため、子ども自身も学習の方向性を理解しやすくなります。
放任でもなく、過干渉でもない“ちょうどいい距離感”が、続けやすさの秘訣です。
コーチが学習スケジュールを子どもに合わせて作成してくれる
学習計画を立てるのって、実は結構むずかしい…。
でも、すららではプロのコーチがその役割を引き受けてくれます。
子どもの性格や家庭のスケジュールに合わせて、無理なく続けられるプランを提案。
たとえば「週3で英語中心」「1日20分ずつ進めよう」など、具体的なペース設定をしてくれるので、家庭学習の指針がはっきりします。
これが“脱・三日坊主”のカギになるんです。
メリット2・不登校・発達障害対応に特化している
すららは、ただの学習アプリではありません。
文部科学省からも推薦されており、不登校や発達障害の子どもたちにも広く活用されています。
一般的な教材ではカバーしきれない「情緒的なサポート」や「学び直しの仕組み」が充実しているため、学校に通えない・通わない選択をした子どもでも、安心して学習を進められます。
しかも、正式に“出席扱い”になるケースも多く、教育現場からの信頼も厚いです。
ADHD、ASD、LDなどの特性に応じた学習支援がなされているので、「今までどの教材も続かなかった…」というお悩みのある家庭ほど、効果を実感しやすいはず。
不登校や発達障害の子向けに、文科省推薦教材として採用されてる実績がある
すららは、ただ人気があるだけの教材ではありません。
文部科学省によって「不登校児童の学習支援に活用できる教材」として正式に紹介された実績があり、公的にも信頼されています。
この実績があるからこそ、学校側に出席扱いの相談をする際もスムーズ。
保護者だけでなく、先生や支援者も安心して選べる教材です。
不登校児童に対して「出席扱い」される学校も多い
すららは、家庭での学習内容や進捗をしっかり記録・証明できる仕組みがあるため、不登校児童に対して「出席扱い」と認定する学校も少なくありません。
すららが提供する学習レポートや診断結果を学校に提出するだけで、一定の条件を満たすことで出席としてカウントされることがあります。
これは子どもの進路にも大きく影響する重要なポイントです。
ASD・ADHD・LD(学習障害)に合わせたカリキュラム&サポートが受けられる
すららは、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠陥・多動性障害)、LD(学習障害)など、さまざまな特性を持つ子どもたちのために、カリキュラムとサポート体制をしっかりと整えています。
たとえば、視覚情報が強い子にはアニメーション中心、集中力が続きにくい子にはスモールステップで学べる設計など。
すららコーチも、特性への理解が深い方が多く、保護者との連携も取りやすいです。
メリット3・学年を超えた「無学年学習」ができる
すららのもう一つの大きな特徴が「無学年学習」。
これは、“学年に関係なく”自分に合ったレベルから学び直したり、先取りしたりできる仕組みです。
たとえば、中学1年生でも小学校の算数からやり直すことができるし、逆に中3の子が高校の英語にチャレンジすることも可能です。
この柔軟性こそが、発達段階にバラつきのある子どもたちにとって最大のメリット。
学び直しが当たり前のようにできるから、「つまずいたまま進む」がなくなり、学習への自信を取り戻すきっかけにもなります。
学年関係なく自由にさかのぼり・先取りできる
一般的な教材では、今の学年の内容に縛られてしまいますよね。
でも、すららは違います。
自分の理解度に応じて、学年を超えて自由に単元を選べるんです。
さかのぼり学習で苦手を克服し、得意な分野はどんどん先取りしていく——そんな柔軟な学びが可能です。
これは「今の学年にはついていけない…」という不安を抱える子にとって、ものすごく心強い設計なんですよ。
発達障害の子は「つまずいたまま進まない」からマイペースに進められるのはポイント
発達障害をもつ子どもにとって、“つまずきを無視して進む”ことは大きなストレス。
すららの無学年式学習なら、どこでつまずいたかをAIが自動で分析し、必要な単元まで戻って丁寧に復習ができます。
つまり、「ちゃんとわかってから次に進む」が自然と実現される仕組みなんです。
自分のペースでOK、誰かと比べなくてOK。
この安心感が継続のカギになります。
メリット4・AI診断×対人コーチングで学習設計が精密
すららの大きな魅力のひとつが、「AI診断」と「人間のコーチング」の両方を活用している点です。
AIが子どもの苦手を瞬時に把握してくれるのはもちろん、その結果をもとに、すららコーチが個別のフォローをしてくれます。
つまり、デジタルの分析力とアナログの思いやりのいいとこ取り。
AIだけでは判断しきれない「子どもの気持ち」や「モチベーションの波」にも対応できるのが大きなポイントです。
さらに、子どもが途中で飽きたり、苦手意識が出てきたときも、コーチが声かけをしてくれるため、学習が止まりにくくなっています。
「学習設計が甘くて続かなかった…」そんな家庭にこそ試してほしい、すらら独自のWサポートです。
AI+人間コーチのWサポートはすららだけのポイント
AIが診断をしてくれる教材は増えてきましたが、その結果を活かせるかどうかは別問題。
その点、すららでは“人”が必ず関わってくれることで、学習の中身が深まります。
AIだけでは完結しない、「人だからこそ気づけるポイント」までしっかりカバーされているのが、すららならではの強みです。
AIだけではフォローしきれない細かい学習状況を、コーチが調整してくれる
子どもは毎日、少しずつ変化していきます。
昨日まではできていたことが、今日は気が乗らなかったり、逆に急に成長が見られたり。
AIでは見逃してしまいがちなこうした“ゆらぎ”に、すららコーチが寄り添ってくれるのが安心です。
AIと人間、それぞれの得意を活かした絶妙なバランスが、子どもの学習を支えてくれます。
メリット5・紙を使わず、すべてデジタルでも「記述力」が鍛えられる
タブレット学習といえば、どうしても「選択式の問題が多い」「記述力が育たない」といった声があります。
でもすららは違います。
デジタル上でもしっかりと“書く力”を鍛えることができるよう、記述重視の設計がされています。
読解問題では、文章を読み取った上で自分の言葉でまとめる形式が多く、「考えて書く力」が自然と身につきます。
さらに、説明力や表現力も同時に伸ばせるため、将来の論述問題や作文対策にも直結。
紙のワークと同等、またはそれ以上の効果を得られるのが特長です。
しかもデジタル完結なので、提出や採点の手間も不要で、親としても手がかからないのが嬉しいポイントです。
「論理的に書く力」「説明する力」にフォーカスしたカリキュラム
ただ「答えを出す」だけでなく、その理由や考え方を説明する力を重視しているのがすららのカリキュラム。
問題を解くだけの学習ではなく、“思考を言語化する”プロセスにフォーカスしているため、自然と論理的思考も育ちます。
テストの点数だけでなく、「伝える力」まで育てたい家庭にピッタリです。
読解+記述のトレーニングがデジタル完結でできる教材は珍しい
読解問題を読み解いて、さらに記述で答える。
このプロセスをタブレット1台で完結できる教材は非常に貴重です。
すららでは、このような“読んで考えて書く”訓練が段階的に組まれているので、国語力だけでなく、総合的な言語能力の土台がしっかり育ちます。
紙の教材に頼らなくても、確かな力がついていくのが嬉しいですね。
メリット6・途中でやめても「再開」がしやすい
勉強って、ずっと続けるのは難しいですよね。
とくに不登校や発達障害をもつ子どもたちは、体調や気分に波があることが多いもの。
そんなときでもすららは「一時中断→再開」がとてもスムーズ。
解約しても学習データが残るため、再開時には続きから学習できるんです。
また、特典キャンペーンの案内が再開者向けに届くこともあるなど、復帰へのハードルを下げる工夫がされています。
「またやりたくなったら戻ってこよう」そんな気持ちになれる安心設計は、他の教材ではなかなか見られません。
続けられなくてもOK。
また始めたくなったら、いつでも戻れる——この柔軟さこそが、すららのやさしさです。
すららは一時中断→復帰が簡単にできる
退会ではなく「解約」や「休会」を選べば、学習データは残ったまま。
再開時は、登録し直す手間も不要で、そのまま続きから学べます。
本人のタイミングで“やりたい”気持ちが戻ったときに、すぐ再スタートできるのが大きな魅力です。
不登校や発達障害の子は「学習ペースに波がある」から、自由に休んで戻れる環境は重要
子どもによっては、学習意欲や体調に波があるのは当たり前。
でも、多くの教材は「続けなければ意味がない」というプレッシャーを与えてしまいがち。
すららは、その波を前提にした設計。
休んでも大丈夫。
戻ってきても笑顔で受け入れてくれる環境がある——これは親にとっても、安心の一言です。
メリット7・出席認定・教育委員会との連携実績がある
すららは、全国の教育委員会や学校との連携実績が豊富で、「不登校支援教材」として正式に採用されているケースもあります。
これは、単なる学習支援ではなく、“公的に認められている教材”としての信頼の証。
すららでの学習記録は「出席扱い」として認定される可能性が高く、中学・高校進学にもプラスに働くことが多いです。
必要書類の提出方法やレポート作成についても、コーチがサポートしてくれるので、保護者の手間も少なく済みます。
「出席日数が足りない」「内申が心配」そんな悩みを持つ家庭にとって、すららはまさに“救いの教材”と言えるでしょう。
すららを使っていると「出席扱い」として学校が認めるケースが多数
すららは文部科学省のガイドラインに基づいた教材として、全国の教育機関で出席扱いに採用されている実績があります。
担任や校長への申請サポートも整っており、書類のフォーマットやレポートの出力機能なども万全です。
これが他の教材との大きな違いです。
不登校支援教材として、学校や病院と連携しているのはすららならでは
すららは単なる家庭学習教材にとどまらず、不登校支援として学校・病院・教育委員会と連携した導入事例が多数あります。
これは、「学習だけでなく、子ども全体を支える仕組みがある」という証。
だからこそ、多くの家庭で選ばれ続けているのです。
【すらら】はうざいと言われる原因は?すららのデメリットについて紹介します
すららは多くの家庭で支持されているタブレット教材ですが、一部では「うざい」と感じる声も存在します。
もちろん、それには理由があります。
連絡の頻度やキャラクターのテイスト、価格面、学習スタイルの自由度など、人によって感じ方に違いが出やすいポイントがあるのです。
特に自主性の強い子や、高学年・思春期の子にとっては、「干渉されている」と感じる場面もあるかもしれません。
ただし、これらは裏を返せば“手厚いサポート”の結果とも言えます。
今回は、すららが「うざい」と言われる原因をひとつひとつ丁寧に紹介しつつ、どんなご家庭に合うのかを見極める参考になればと思います。
原因1・すららコーチやサポートからの連絡がしつこいと感じることがある
すららは他のタブレット教材と違い、専任の「すららコーチ」がつきます。
これは手厚いサポートとして喜ばれる反面、「頻繁に連絡が来る」と感じる人も。
特に自主性が高いお子さんや、「放っておいてほしいタイプ」の子にとっては、コーチのフォローが“監視”のように感じてしまうこともあるようです。
親としては安心感がある一方で、子ども本人の性格に合わない場合は、ストレスの原因になり得ることも。
連絡の頻度は調整できることもあるので、必要に応じてコーチに相談するのがベストです。
自主的にやりたい子や、放っておいてほしい子には合わないこともある
自分のペースで進めたい子どもにとって、外部からのアドバイスや声かけは“干渉”と感じてしまうことも。
すららは手厚いがゆえに、受け取る側の性格によっては「過剰」と受け取られる可能性があります。
原因2・「やらされ感」が強くなるとプレッシャーに感じることがある
すららはAIが学習計画を自動作成し、毎日の学習を可視化してくれるのが魅力ですが、これが「縛られている」と感じてしまう子もいます。
「今日は疲れているから休みたい」と思っても、通知やリマインドが届くとプレッシャーに。
もちろん計画の調整は可能ですが、子ども自身が管理できないと「やらされている感」が強くなってしまう場合があります。
特に、マイペースに学習したいタイプの子には、柔軟性が足りなく感じられるかもしれません。
自動で学習計画を作ってくれるAIに縛られていると感じてしまうことがある
学習計画を自分で立てるより、AIに任せた方が効率的…と思う一方で、自由に勉強したいタイプの子には「機械に決められている」感覚がストレスになることも。
これは性格との相性の問題です。
原因3・キャラクターやナビゲーションが子どもっぽい・くどいと感じることがある
すららではアニメーションのキャラクターが授業を進行し、対話形式で子どもをサポートします。
この仕組みは低学年や発達障害のあるお子さんには非常に効果的ですが、一方で中学生や思春期の子どもには「子どもっぽすぎて恥ずかしい」「くどい」と感じられることもあるようです。
特に男子の場合、「キャラが話しかけてくるのがうざい」と感じてしまう声も。
楽しめるかどうかは、年齢と性格に左右される部分が大きいので、体験版などで確認しておくのが安心です。
高学年や思春期の子にはキャラクターがうざいと感じることがある
キャラクターのテンションや表現が合わないと、「子ども扱いされてる」と感じてしまうこともあります。
特に中学生以上になると、落ち着いた教材の方が好まれる傾向があるため注意が必要です。
原因4・勧誘や営業の印象が「しつこい」と感じる人がいる
資料請求や無料体験のあとに、メールや電話での案内が届くことがあります。
これはサポート体制の一環ですが、中には「営業がしつこい」と感じる保護者も存在します。
とくに“静かに見極めたい”タイプの人にとっては、丁寧なフォローがかえって逆効果に映ることも。
とはいえ、不要な場合は「今後のご連絡は不要」と伝えるだけでストップできるので、過剰な心配は不要です。
ただし、この“しつこさ”をSNSなどでネガティブに拡散されてしまうことが、「うざい」と言われる一因になっています。
「連絡が頻繁」と感じると、SNSでは「うざい」と言われることがある
メール・DM・電話などの案内が重なると、「勧誘がしつこい」と感じる人も。
すらら側はあくまで親切心で連絡しているのですが、タイミングや回数によってはマイナスの印象に映ることもあります。
原因5・料金が高く感じる割に効果が実感できない場合がある
すららは入会金+月額料金が必要な教材で、他の家庭学習アプリよりやや高めと感じる方もいます。
費用に見合うだけの学習効果が得られれば納得感はあるものの、子どもが自主的に学習しないと成果は感じづらくなります。
とくに保護者が「すららを使わせているだけで成績が上がる」と期待しすぎると、現実とのギャップに不満を感じることも。
効果を最大限に引き出すには、子どもの性格と相性が良いか、親が適度に関わるかどうかがカギになります。
子供が1人で学習に取り組めないままだと勉強効果を実感できない保護者もいる
どんなに良い教材でも、使いこなさなければ意味がありません。
子どもがすららに馴染めなかったり、日々の学習を習慣化できないと、結果的に「料金が高いだけ」と感じてしまうケースもあるようです。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは高い?すららの料金プランについて紹介します
家庭用タブレット教材「すらら」は、その学習効果や柔軟な学習スタイルが注目されていますが、一部では「料金が高いのでは?」という声も見られます。
確かに、すららは月額制+入会金が必要なため、手軽な無料アプリや紙教材と比べると初期費用・維持費がやや高めに感じられるかもしれません。
しかしその一方で、「兄弟で使える」「科目追加自由」「無学年制」「すららコーチのサポート付き」など、内容の充実度は価格以上という評価も多く見られます。
今回は、そんなすららの料金体系について、具体的な入学金や月額料金をコース別に解説しつつ、「本当に高いのか?」「他の教材と比べてコスパはどうか?」という疑問にお答えしていきます。
すらら家庭用タブレット教材の入学金について
すららを始める際に必要となる入学金は、選択するコースによって異なります。
たとえば、「小中・中高の3教科コース」や「小学の4教科コース」は11,000円(税込)の入学金がかかります。
一方で、「小中・中高の5教科コース」の場合は、入学金は7,700円(税込)と、若干お得な設定です。
この金額を「高い」と感じるかどうかは、受けられるサービスとのバランス次第。
すららでは、無学年学習の自由度や、AI×人によるコーチングの手厚さ、家庭用教材には珍しい出席扱い対応サポートなどがあり、単なる教材以上の“教育サービス”という側面も持っています。
さらに、キャンペーン時にはこの入会金が無料になるケースもあるため、タイミングを見てお得にスタートすることも可能です。
| コース名 | 入学金(税込) |
| 小中・中高5教科コース | 7,700円 |
| 小中・中高3教科、小学4教科コース | 11,000円 |
すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について
すららの3教科コースは「国語・数学・英語」の主要科目に特化したコースです。
特に中学生にとっては、内申点や定期テストに直結しやすいこの3教科に絞って集中的に学習できるのが魅力です。
小学生の場合でも、「英語に早めに慣れておきたい」「算数や文章問題が苦手だからしっかり復習したい」という家庭に向いています。
また、英語は「聞く・読む・話す」に対応した構成になっており、小学生〜中学生の基礎固めに最適な内容となっています。
すららの無学年式学習は、この3教科でももちろん有効で、たとえば「小6で中1の英語に挑戦したい」「中2だけど小5の算数からやり直したい」といった柔軟な学習が可能です。
必要な科目だけに集中したい方にとって、コスパの良い選択肢となるのがこの3教科コースです。
毎月支払いコースの料金
すららの3教科コース(国語・数学・英語)を「毎月払い」で契約する場合、小中コース・中高コースともに月額8,800円(税込)となっています。
この金額には、すららコーチによる学習計画の作成やサポート、AIによる自動出題、進捗レポートの作成といったサービスもすべて含まれています。
学年に縛られない「無学年式」の教材設計のため、つまずいた単元にさかのぼって学び直すことも、得意な分野をどんどん先取りすることもできます。
家庭用タブレット教材でこの価格は一見高く感じるかもしれませんが、紙教材や家庭教師、塾などと比較すると、手厚いサポートを考慮して「むしろ割安」と評価する保護者の声も多いです。
毎月の支払で始められるため、気軽にスタートできる点もメリットです。
| コース名 | 月額 |
| 小中コース | 8,800円 |
| 中高コース | 8,800円 |
4ヵ月継続コースの料金
4ヵ月継続コースは、「短期でやめるかも…」と迷っている家庭には少しハードルが高いと感じるかもしれませんが、継続前提で学習を進めたい方にとっては確実にお得な選択です。
通常の毎月払いより約500〜600円安くなるため、1年間の合計額で見ればかなりの節約に。
しかも、機能やサポートは通常コースとまったく同じ。
特に学習習慣が身についてきた子や、数ヵ月単位でじっくり取り組みたいご家庭には「実質最安のフルサポート型」と言っても過言ではありません。
ただし、途中解約には解除料金が発生します。
契約前に「どのくらい続けられそうか?」をしっかり確認することが絶対条件。
短期で切るならおすすめしません。
長期的に見る人には断然アリです。
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 8,228円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/4教科(国・数・理・社)コース月額料金について
理科と社会を含む4教科コースは、「主要3教科だけでは不安」「テスト対策に広く対応したい」家庭にとってベストな選択肢です。
学校の授業の補完だけでなく、先取りや復習まで柔軟に対応できるのが特徴。
毎月払いと継続コースで金額差はありますが、どちらもコスパは非常に良好です。
理科・社会が苦手な子は多く、後回しにされがちな教科でもあるからこそ、家庭でしっかり強化できる教材の価値は大きいです。
他社の教材だと理社は追加料金だったり、そもそも対応していないことも。
すららはこの4教科パッケージでトータルに力を付けさせてくれる点が強み。
教科ごとのつまずきを放置せず、AIがピンポイントに出題する仕組みは、他の教材ではなかなか真似できません。
| コース名 | 月額 |
| 小学コース(毎月支払いコース) | 8,800円 |
| 小中コース(4ヵ月継続コース) | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/5教科(国・数・理・社・英)コース月額料金について
正直に言って、すららの5教科コースは「本気で内申点や受験を意識している家庭」以外は不要かもしれません。
でも、逆に言えば、この1つで学校の全教科をカバーできるのは強烈なアドバンテージです。
価格帯は1万円超えと一見高く見えますが、家庭教師1時間分にも満たない金額で「AI分析+プロコーチ+教科バランス」のすべてが揃うのは破格。
しかも兄弟で使い回し可能。
この「1契約=家族全体が使える」柔軟さがあるから、ファミリー層にはかなり魅力的です。
英語もしっかりスピーキング対策まででき、理社の要点学習もある。
結局、5教科すべてを丸投げできる教材って、実はほとんどないんですよね。
真面目に点数を上げたいなら、他の選択肢が霞むレベルの内容です。
毎月支払いコースの料金
毎月支払いコースは「とりあえず試してみたい」「いつでもやめられる安心感が欲しい」という方に向いています。
すららのすごいところは、初月からフル機能が解放され、プロコーチのサポートも標準でついてくる点。
この価格帯でAIと人間の両輪サポートが付く教材は、他に見当たりません。
とはいえ、毎月払いは長期で見ればわずかに割高になります。
短期で成果を試したい場合や、合うかどうか不安な場合はまずはこのプランから始めて、継続できそうなら途中で4ヵ月コースへ移行するのもアリ。
なお、途中で休会や解約もできますが、毎月25日締切などのルールもあるので注意が必要です。
初期投資を抑えたいなら、最初の1〜2ヵ月はこのプランで様子を見るのが現実的です。
| コース名 | 月額 |
| 小学コース | 10,978円 |
| 中高コース | 10,978円 |
4ヵ月継続コースの料金
継続前提で利用するなら、4ヵ月コースは文句なしでお得。
1教科あたりで見ると破格の月額でプロ講師のコーチングが受けられ、教材の質も高水準。
長期視点で「どうせ続けるなら安く済ませたい」と考えるなら、このプランを選ばない手はありません。
ただし、途中解約には違約金が発生するため、1〜2ヵ月でやめる可能性があるなら選ぶべきではないのも事実。
コスパ最強といえるのは「計画的に学習を続けたい」「家庭内で学習を習慣化できている」場合のみ。
お試し気分では手を出さないほうがいいですが、覚悟があるなら間違いなく最適なプランです。
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 10,428円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 10,428円 |
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの勉強効率や勉強効果は?コースについて紹介します
すららは「勉強効果が見えにくい教材」と思われがちですが、実は、学年や発達段階に応じて設計されたAIと対話型学習が強み。
特に「理解→定着→応用」のサイクルを短期間で回せるように設計されているのが最大の特徴です。
また、学力だけでなく、自信や学習の習慣化という側面でも好影響があると評価されており、保護者からの満足度も高い傾向にあります。
すららは3教科から5教科まで柔軟に選べるので、子どもの苦手科目に応じて選択できるのも魅力。
ここでは、それぞれの教科コースごとに期待できる勉強効果を紹介します。
すらら3教科コース(国・数・英語)の勉強効果について紹介します
3教科コースは、特に中学生や「主要科目だけまず強化したい」という子におすすめです。
すららの国語・数学・英語は、いずれも基礎〜応用までのステップが細かく区切られており、苦手な単元をピンポイントで対策できるのが魅力。
とくに英語は「単語・文法・発音・読解」まで網羅しており、英検などの資格試験にも対応可能な内容です。
また、短時間で「できた!わかった!」という成功体験が得られることで、モチベーションを維持しやすいのも特徴です。
基礎学力を固めることで、学校の授業理解度やテストの点数アップにも直結します。
勉強効果1・基礎力の定着がとにかく早い
すららの学習スタイルは「1ユニット10〜15分」単位のスモールステップ。
そのため、集中力が持たない子でも着実に理解を積み重ねることができます。
アニメーションと対話形式で進むため、ただ問題を解くだけでなく、なぜ間違えたか・どう直すかが自然と身に付き、短期間での基礎力定着が可能になります。
勉強効果2・短時間で「できる→わかる→応用」の流れを作ってくれる
すららは単なる「反復学習」ではありません。
問題を解きながら「対話で理解」→「解き直しで定着」→「応用問題で実力アップ」という流れを自動で構築してくれます。
AIによって苦手を特定し、個別に復習内容を提示してくれるので、効率よく勉強できるのが特長です。
勉強効果3・中学生は主要3教科で内申点が決まるから「点数を上げたい」「定期テストで成果を出したい」という目的に直結する
特に中学生にとって、内申点に直結するのが国語・数学・英語の3教科です。
すららは定期テスト対策に強く、教科ごとに「まとめテスト」や「確認ドリル」があるため、普段の学習がそのままテスト対策になります。
自宅でしっかり取り組むことで、内申点アップにも貢献できる教材です。
すらら4教科コース(国・数・英語・理科または社会)の勉強効果について紹介します
4教科コースは、主要3教科に加えて、理科または社会のどちらかを選択するコースです。
理科・社会は暗記要素が強く、どうしても後回しにされがちな教科。
でも、すららでは視覚的に理解できるスライドやアニメーションを使いながら、しっかり記憶に残るよう工夫されています。
反復テストや要点まとめ機能もあるため、「苦手だけど点数に直結する教科」を伸ばすには非常に向いています。
時間対効果も高く、1教科10分〜20分の短時間集中で取り組めるので、テスト前の学習効率が劇的に向上するという声も多く寄せられています。
勉強効果1・理科・社会は、「繰り返し学習」と「確認テスト」で記憶の定着率が高まる
理社は暗記と理解のバランスが重要な教科。
すららでは、AIがその子に合った復習タイミングを判断して、効率的な記憶定着ができるように設計されています。
間違えた問題は自動で再出題されるので、忘れかけたタイミングで思い出すトレーニングが可能です。
勉強効果2・ポイントを押さえた要点学習で、時間対効果がとてもいい
理社のテスト対策では、範囲を「広く浅く」学ぶよりも、要点に絞って「深く覚える」ことが効果的です。
すららはその考え方に基づいて、「覚えるべきポイント」を明確に提示してくれるため、短時間で高得点につながる学習ができます。
反復学習との相性も抜群です。
勉強効果3・通常の塾や学校より、短時間で理解→テスト対策ができるところが強み
塾では週1〜2回、学校でも1日1教科の時間しかありませんが、すららなら「毎日理社に触れる」ことが可能です。
1日15分〜20分での学習でも効果が出る仕組みがあるので、限られた時間の中でもしっかり点数アップにつながります。
すらら5教科コース(国・数・英語・理科・社会)の勉強効果について紹介します
5教科対応のすららは、受験や通知表の内申点を総合的に上げたい子にぴったり。
特に中学生にとって、5教科のバランスは内申点に直結し、高校受験にも強く影響します。
すららでは全教科の苦手単元をAIが分析し、個別に復習計画を提示。
日々の学習がそのまま成績アップにつながるように設計されています。
特に「全体を底上げしたい」「苦手を放置せずに均等に伸ばしたい」という保護者には大人気。
塾と違って、科目のバランスを自由に調整できるのも大きなメリットです。
勉強効果1・全教科を満遍なくカバーし、内申点・通知表UPに直結/ 特に中学生の内申点は「5教科バランス型」が必須
中学の通知表では「苦手な教科が1つでもあると総合評価が下がる」傾向にあるため、すべての教科をバランス良く学ぶことが重要です。
すららの5教科コースは、AIとコーチの両輪サポートでバランスよく対策ができ、内申点アップを目指すには最適な構成です。
勉強効果2・高校受験にも直結する実力アップ/模試や過去問対策にも応用できる
すららで身につく力は、ただの教科知識ではなく「考える力」や「記述力」も含まれます。
そのため、模試や過去問でも応用できる思考力が育ち、受験にも対応可能です。
基礎だけでなく、発展問題にも挑戦できる設計なので、志望校に合わせて強化できます。
勉強効果3・ 5教科すべてAIが自動で弱点を分析し、学習計画を立ててくれるから効率的
5教科ともなると、自力で計画を立てるのは至難の業。
しかし、すららではAIが苦手単元を自動で抽出し、「どこを重点的にやるべきか」を提案してくれるため、無駄のない学習ができます。
さらに、コーチと相談しながら微調整できるのも安心です。
勉強効果4・他の教材や塾より、時間あたりの学習効果は高いと感じる人が多い
家庭で取り組む教材の中でも、すららは「学習効率」に優れていると感じる声が多いのが事実。
動画と対話、ドリルとテストのバランスが良いため、ただの暗記型では終わらず、理解重視の学習が可能。
忙しい中学生にも適した設計になっています。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは発達障害や不登校でも安心・安全に使える理由
「うざい」といった声も一部で見られるすららですが、実は発達障害や不登校の子どもにこそ適した設計がされています。
特に注目されているのが、ストレスを感じにくい学習環境と、本人の特性に寄り添う「ユニバーサルデザイン」。
学校の授業についていけずに自信を失ってしまった子や、集団の中で過度なプレッシャーを感じていた子でも、すららなら自分のペースで学び直すことができます。
学習内容はもちろん、学び方そのものがやさしく設計されているため、安心して続けやすいのが特徴。
ここでは「なぜ安心・安全に使えるのか」を具体的に解説します。
安全な理由1・「本人のペースで学習できる」からプレッシャーがない
すららは「無学年式学習」を採用しているため、学年にとらわれず、得意なところはどんどん先に、苦手なところはじっくり戻って学ぶことができます。
この自由度の高さが、プレッシャーを感じやすい発達障害の子どもにぴったり。
たとえばADHDの子は集中力が短いため、調子の良いタイミングに合わせて一気に学べるのがメリット。
また、ASDの子は一定のルーティンが安心材料になるため、「毎日同じ時間に、決まった流れで学べる」ことで学習が安定しやすくなります。
学校の進度や周囲のペースに左右されず、完全に“自分のペース”を大切にできる学習環境です。
学校の授業の「遅れ」や「先取り」を気にせず、マイペースに学べるから、ストレスが少ない
学校ではどうしても「授業についていけない」ことで焦りや劣等感を抱きやすいもの。
すららは、現在の学力を基準にスタートでき、つまずいた単元までさかのぼって学べるため、「分からないまま進む」ことがありません。
自信を持ちながら勉強を進められる環境は、ストレスの軽減にもつながります。
ADHDタイプの子は「集中できる時に一気に」、ASDタイプの子は「毎日決まったペースで」、それぞれに合った使い方ができる
ADHDの子は集中力の波が大きいため、無理に毎日一定時間を強いるよりも「集中できる時に一気に進める」ほうが効果的です。
逆に、ASDの子には「毎日同じ時間・同じ順序で学ぶ」ことで安心感が生まれます。
すららは、どちらの特性にも柔軟に対応できる教材なので、個々の子どもの特性に合った活用が可能です。
安全な理由2・「対面の緊張や不安がゼロ」だから取り組みやすい
人とのやりとりにストレスを感じやすい子どもにとって、オンライン教材は安心材料になります。
すららではアニメーションキャラクターが優しくナビゲートしてくれるため、「間違えて怒られる」「恥ずかしい思いをする」といった不安を一切感じることなく学習ができます。
また、対話形式で進むレッスンは、子どもに寄り添う語り口で構成されているため、自然に取り組みやすく、初学者でも「怖くない」「やってみようかな」と思えるような心理的ハードルの低さが魅力。
対人関係の緊張が原因で学習に取り組めなかった子どもたちにとって、大きな味方になる教材です。
アニメーションのキャラが優しく教えてくれて、正解でも不正解でも感情的な反応をされることはない
すららでは、子どもに語りかけるキャラクターが「優しい先生役」として登場します。
どんなに間違えても怒ることはなく、むしろ「こうやったら解けるよ」と丁寧に解説してくれるのが特徴。
否定や怒りではなく、励ましや導きのスタンスだから、子どもが委縮せずに学習を続けられるのです。
人とのコミュニケーションに不安がないから安心して学ぶことができる
発達障害のある子の中には、対人関係に強い不安を抱く子もいます。
すららは完全オンライン&自宅学習だから、人と接するストレスなしに学びを進めることが可能。
誰かに見られている不安や、質問のタイミングに困るといった悩みもなく、自分のリズムで安心して取り組むことができます。
安全な理由3・発達障害に対応した「ユニバーサルデザイン」設計
すららは単なる「一般向け教材」ではなく、発達障害や学習障害のある子どもにも対応できる設計がされています。
視覚・聴覚の両方から情報を得られるマルチモーダル学習、文字が見やすいフォント、音声スピードの調整など、誰にとっても「使いやすい」構造=ユニバーサルデザインが徹底されています。
また、情報処理に時間がかかる子どもに対しても、ペースを合わせてくれるのが大きな特徴です。
どの子にも「つまずかせない・取り残さない」安心の設計だからこそ、障害の有無に関係なく学習を継続しやすいのです。
すららは「誰でも理解しやすく、つまずきにくい」ように作られている
たとえば、問題文が長すぎないように工夫されていたり、1画面に表示される情報量を制限するなど、注意が散りやすい子への配慮も随所にあります。
説明は必ず図解や例を交えて進むため、「わかりにくい」が発生しにくい教材です。
読字障害(ディスレクシア)、言語理解に時間がかかるASDの子にも分かりやすい
文字を読むのが苦手な子には音声での読み上げ機能、言葉の意味をとらえづらい子にはイラストやアニメーションを活用した解説がされており、視覚・聴覚の両方から情報を得ることができます。
この設計が、読み書き障害のある子やASDの子にも「分かりやすい」と支持されています。
「視覚優位」「聴覚優位」どちらのタイプの子にもマッチしやすいのが特長
視覚優位の子はスライドや図表を通して、聴覚優位の子は音声ナレーションを通じて情報を吸収できます。
すららはこのどちらにも対応しており、どんな学び方のタイプでも「自分に合っている」と感じやすい教材です。
「音声速度」を調整できる機能もあるから、「ゆっくり聞きたい」「早く進めたい」など、子どもの特性に合わせられる
理解力や集中力には個人差があります。
すららでは音声ナレーションの速度を変更できるため、「じっくり聞きたい」子や、「テンポよく進めたい」子どもにも対応可能。
特性に合わせた細かい設定ができる点が、長く続けやすい理由のひとつです。
安全な理由4・間違えても怒られない・恥をかかない設計
すららは、間違いを責めるのではなく、「なぜ間違えたのか」「どう直せば良いか」を丁寧に導く仕組みが整っています。
これは、失敗を避けたい気持ちが強い発達障害の子どもにとって、とても大きな安心材料です。
たとえば学校や塾では、間違えた瞬間に「できない子」というレッテルを貼られたと感じてしまいがちですが、すららではそのような“評価される空気”がありません。
間違いは成長の一歩として扱われ、解説もアニメーションや音声で優しくサポートしてくれるので、自然と「次こそはできるようにしよう」と前向きな気持ちになれます。
恥ずかしさを感じず、学び直しを素直に受け入れられる環境があること。
それこそが、継続学習の最大のカギです。
「否定」ではなく「納得」させてくれるから、自己肯定感が下がりにくい
すららでは、子どもの間違いに対して「それは違う」ではなく、「こうするともっと良くなるね」といったアプローチをします。
だからこそ、子どもは失敗しても自分を否定されたと感じにくく、自信を失わずに学習を続けることができます。
学校や塾では感じがちな「恥ずかしい」「できない」といったネガティブ感情を抱きにくい
クラス全体の前で間違える経験は、子どもにとって大きなストレスになることがあります。
しかし、すららは1人で静かに学べるので「恥ずかしい」という感情を抱きにくく、自分のペースで取り組むことができます。
安全な理由5・「ゲーム感覚」の楽しい仕組みで続けやすい
すららの教材は、子どもが楽しく学べるように「ゲーム要素」がしっかり組み込まれています。
たとえば、学習を進めるごとにキャラクターが褒めてくれたり、クイズ形式で進むレッスンなど、「遊び心のある教材設計」がされているのが魅力です。
特に、集中力が続きにくいADHDタイプの子どもは「結果がすぐに見える」「褒められる」といったポジティブなフィードバックがあることで、やる気が持続しやすくなります。
楽しいから続けられる。
続けられるから成果が出る。
この好循環を生み出すには、学びの中に「楽しさ」があることが非常に大切です。
飽きずにコツコツ続けられる設計だからこそ、すららは“継続が難しい子”にもフィットしやすいのです。
アニメキャラクターがナビゲートし、クイズ形式やゲーム感覚の要素があるから「もうちょっと続けたい」と思わせる工夫がされてる
キャラクターがテンポよく会話を進めたり、選択式クイズで正解するたびに褒められると、「あと1問だけ!」とついつい続けたくなります。
学習=苦行ではなく、“遊びの中の知育”として捉えられるのが魅力です。
ADHDの子は「すぐに褒められる」「すぐに結果が出る」とやる気が続きやすい傾向がある
ADHDの子は長期的な目標よりも、目の前のご褒美やフィードバックがモチベーションに直結します。
すららの即時フィードバックはその特性にピッタリで、「またやりたい」と感じる気持ちを自然に育ててくれます。
安全な理由6・「すららコーチ」がいるから親子で抱え込まなくていい
発達障害や不登校の子をサポートする中で、保護者自身が抱える負担も非常に大きなものです。
「毎日勉強を見なきゃ…」「何をやらせたらいいのか分からない」などの悩みを、すららでは「すららコーチ」がサポートしてくれます。
学習の進捗を見ながら、必要に応じてアドバイスをくれたり、つまずいているポイントを分析してくれたりと、“第3の頼れる存在”として心強い存在です。
特性理解に長けたコーチも多く、ADHDやASD、LD(学習障害)に対する知識も持っているから、安心して相談できます。
親が全部抱えなくていいというのは、継続にも精神的なゆとりにも直結します。
ADHDやASD、学習障害の特性を理解した対応をしてくれるコーチが多い
コーチは、学習支援だけでなく、子どもの性格や状態に合わせたサポートもしてくれます。
「言い方を工夫してくれた」「褒めてくれて本人が自信を持てた」といった声も多く、単なる機械的な支援とは違う温かみがあります。
コーチが学習計画を立てたり、つまずきポイントを教えてくれる
どこから学べばいいのか、何をやればいいのか。
そんな迷いをコーチがすべて整理してくれます。
進捗が見えるだけでなく、必要なアクションも明確なので、親も子も安心して進められるのが魅力です。
安全な理由7・「完全オンライン」だから家で完結できる
通学や外出に不安がある子どもにとって、「完全オンラインで学べる」というのは大きなメリット。
すららはネット環境とタブレット1台あれば、自宅で完結できる教材です。
外出が困難な時期でも継続的に学べるだけでなく、親の送迎や準備の手間も省けるため、家庭内での学習ハードルがぐっと下がります。
また、学校の授業に出られなくても、すららで継続的に学習を進めることで、「学習の穴」を防ぎ、子ども自身の自信にもつながります。
家にいながら、自分のペースで、安心して学べる。
それこそがすららの「安全性」の大きな理由の一つです。
タブレット1台あればできるから、環境づくりもシンプルだし、親の負担も減る
特別な教材や準備は不要。
タブレットとWi-Fi環境さえあればすぐに始められるので、「明日からでもできる」というシンプルさが魅力。
親が準備や管理で疲弊しないのも大きなポイントです。
通学できない間も学習の「穴」を作らず、自信を持たせてあげられる
学習が止まると「自分はダメだ」と感じてしまう子もいますが、すららがあれば、自宅にいながらしっかり勉強が進められます。
成果が目に見えることで、子ども自身の自己肯定感も高まりやすくなります。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの解約・退会方法について紹介します
すららは非常に自由度の高い家庭用タブレット教材ですが、実際に利用していく中で「一旦やめたい」「環境が変わったから解約したい」と思うこともありますよね。
このページでは、すららの【解約】【退会】についてわかりやすく解説していきます。
特に、すららでは「解約」と「退会」の意味が違うので、そこを正しく理解して手続きを進めないと、思わぬトラブルに繋がる可能性もあります。
この記事では、解約・退会それぞれの意味や手順、注意点を詳しくまとめましたので、これから手続きを考えている方はぜひ最後までチェックしておいてくださいね。
すららの【退会】と【解約】は意味が異なる!それぞれの違いについて解説します
まず最初におさえておきたいのが、すららにおける「解約」と「退会」は別物という点です。
解約は単に利用を一時停止する手続きのことであり、学習データやアカウントはそのまま残ります。
一方、退会はすららの会員資格そのものを終了させる手続きです。
退会すると、学習履歴や個人情報が完全に削除されるため、元のアカウントでの再開はできません。
もし再びすららを利用したくなった場合、新たに入会し直し、入会金も発生する場合があるので注意が必要です。
この違いを知らずに「解約だけしてたと思ったら退会してた!」という失敗を防ぐためにも、事前に整理して理解しておきましょう。
すららの解約は「利用を停止すること」。
毎月の支払い(利用料)を止める手続き。
すららの「解約」とは、学習システム自体の利用を一旦ストップすることを指します。
具体的には、毎月の受講料(利用料)の支払いを停止し、サービスへのログインや利用はできなくなりますが、アカウントや学習履歴などのデータは削除されません。
つまり、「また学習を再開したいな」と思ったときに、簡単に復活させることが可能です。
なお、注意点として解約の申請は【毎月25日まで】に行う必要があり、それを過ぎると翌々月の解約になってしまいます。
解約手続きだけでは、完全に情報が消えるわけではないので、学習記録を残しておきたい人や、いつか再開する可能性がある人には、まず「解約」を選ぶのがおすすめです。
すららの退会は 「すららの会員そのものをやめること」。
データも消える。
一方で「退会」は、すららの会員登録自体を抹消する手続きです。
退会をすると、これまでの学習データ、到達度記録、個別に設定した学習プラン、問い合わせ履歴など、すべての個人情報が完全に削除されます。
また、退会後に再度すららを利用したい場合は、あらためて新規入会手続き(+入会金支払い)が必要になるため、ハードルが高くなります。
さらに、退会してしまうとキャンペーン特典の対象外になるケースもあり、再開時にお得な条件での復活ができないこともあります。
もし「また再開するかも」と少しでも思っているなら、軽率に退会せず、まずは【解約だけ】にしておくのが賢い選択です。
すららの解約方法1・すららコール(サポートセンター)に電話
すららを解約したい場合、まず最初にやるべきは「すららコール(サポートセンター)」への電話連絡です。
実は、すららでは公式サイトやマイページからWEBだけで簡単に解約完了する仕組みは用意されていません。
必ずサポートセンターに直接電話をかけ、本人確認を経て解約申請を行う必要があります。
少し面倒に感じるかもしれませんが、スタッフが丁寧に対応してくれるので、特別難しいことはありません。
ここで本人確認情報(登録氏名・ID・電話番号など)を伝えるため、事前にメモしておくとスムーズです。
電話対応時間は平日のみ(9:30~17:30など)なので、余裕をもって連絡することをおすすめします。
| 【すららコール】
0120-954-510(平日10時~20時 土日祝休み) |
すららの解約はメールやWEBからは受け付けていない
すららの解約を希望する場合、WEBサイトやマイページから手続きが完了できると考えてしまう方も多いのですが、実際には「メール」や「WEBフォーム」からの解約は一切受け付けていません。
これはセキュリティの観点や本人確認の重要性を考慮した運営方針によるものです。
解約をするには、必ず「すららコール」と呼ばれる専用のサポートセンターへ電話をする必要があります。
電話対応のため、営業時間内での連絡が必須となるため、余裕をもってスケジュールを立てましょう。
また、解約の受付は平日のみのことが多く、月末が近づくと電話が混み合うこともあるので、可能であれば月中には連絡を済ませておくと安心です。
すららの解約方法2・電話で本人確認/登録者氏名・ID・電話番号など
解約の電話をかけたら、まず必要になるのが「本人確認」です。
すららの契約情報は個人情報が含まれているため、サポートセンターでは本人確認を徹底しています。
オペレーターに「登録者氏名」「ユーザーID」「登録電話番号」などを伝えることで本人確認が行われ、問題がなければ次の解約手続きへ進む流れになります。
事前にこれらの情報を手元にメモしておくと、スムーズに対応が進みます。
特に、IDは登録完了時のメールに記載されているので、過去のメールを確認しておくと便利です。
また、家族が代理で連絡する場合は、本人の承諾確認や追加の情報提示が求められることがあるので注意が必要です。
すららの解約方法3・解約希望日を伝える/日割り計算はされません
本人確認が完了したら、次は「いつ解約したいのか?」という希望日を伝えるステップに進みます。
ただし注意点として、すららでは月額料金が【日割り計算されません】。
つまり、月の途中で解約してもその月の受講料は全額発生するという仕組みです。
そのため、月初に解約しても月末に解約しても金額は同じ。
だからこそ、できるだけ月末ギリギリまで利用してから解約するのが経済的といえるでしょう。
また、申請の締め切りは【毎月25日】です。
25日を過ぎてしまうと、翌月分の受講料も発生してしまうため、「ギリギリでも25日までに手続きを完了させる」ことが重要なポイントです。
すららの退会方法について/解約手続き完了後に退会依頼をする
「すららを完全にやめたい」という場合には、解約だけでなく「退会手続き」も必要です。
ただし、退会は解約が完了してからしか申請できない流れとなっており、まずは月額利用料の停止(=解約)を済ませておく必要があります。
退会を希望する場合は、解約の電話の際にそのままオペレーターに「退会も希望します」と伝えるだけで大丈夫です。
退会処理が受理されると、登録していたメールアドレス・学習データ・個人情報がすべて削除され、再びすららを使いたくなったときには新たに入会金を支払って再登録する必要があります。
再利用の可能性が少しでもあるなら、退会せず解約だけに留めるのが安心です。
すらら解約の電話時に退会希望の旨を伝える
すららを解約する際に、同時に「退会」も希望する場合は、電話をかけたタイミングでオペレーターにその旨を伝えておきましょう。
退会の申請は別途WEBからなどの手続きはなく、電話で解約と同時に申し出ればその場で案内してもらえます。
具体的には「登録情報をすべて削除したいので退会もお願いします」と伝えることで、退会用の案内メールを送ってもらえる場合もあります。
手続きに不備がないよう、オペレーターとしっかり確認を取りながら進めましょう。
なお、一度退会を完了させてしまうと、元の学習データやコーチからのフィードバックなどはすべて失われるので、よく考えてから決めることが大切です。
すらら解約後に退会をしなくても全く問題はありません(料金の支払いは停止します)
すららを解約しても「退会」しないまま放置しておいても特に問題はありません。
料金の支払いは解約と同時にストップするため、使っていない間に追加費用が発生することもありません。
また、退会していなければ、アカウント情報や学習履歴はそのまま保管されており、「やっぱりまた使いたい」となったときに、再契約のみで簡単に再開できるメリットがあります。
再開時には入会金が不要になる場合が多いため、学習データを保持したまま一旦離れたい人は、あえて退会せずに「解約だけ」にしておくのが非常におすすめです。
すららの利用を再検討する可能性があるなら、まずは「解約」で様子を見ると良いでしょう。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの効果的な使い方について紹介します
「すらら」はただタブレットを渡しておしまい、という教材ではありません。
むしろ、子どもの特性や生活リズムに合わせた使い方次第で、効果が何倍にも変わる“育てる教材”です。
学年別・学習段階別におすすめの使い方を押さえておけば、無理なく継続できるだけでなく、学習効果もしっかり実感できます。
特に小学生や中学生のように習慣がつきやすい年代では、家庭での取り組み方や声がけひとつで、学びのモチベーションが劇的に変わります。
ここでは、小学生・中学生に合わせた効果的な使い方を、具体例と共にご紹介していきます。
すららが「うざい」どころか、子どもに寄り添い、親もラクになる“頼れる教材”に変わるヒントが見つかるはずです。
【小学生】すららの効果的な使い方について紹介します
小学生にとって、学習習慣を作ることは最も重要なステップです。
すららは無学年式なので、小1でも小6でも、それぞれに合わせたペースで始められます。
ポイントは「楽しさ」と「継続」を軸に設計すること。
親子でゲームのように楽しみながら取り組むと、勉強が日常の一部になります。
また、小学生は自己管理が難しい時期なので、親の関わり方も重要。
「ほめる」「一緒にやる」「成果を可視化する」など、モチベーションを継続できる環境づくりが大切です。
特に低学年では、短い時間でも集中する癖をつけることが、後の学力形成にも大きく影響します。
使い方1・「短時間×頻度」でリズムを作る/1回20〜30分を目安に、毎日少しずつ続ける
長時間やろうとすると、子どもはすぐ飽きてしまいます。
すららは1回20〜30分程度のスモールステップ設計なので、集中力が続きやすい構造になっています。
1日1ユニットでも「続けること」に価値があると親子で共有し、無理のない時間設定で進めるのがコツです。
週に3回以上を目標にすると、自然と習慣化できます。
使い方2・「ごほうび制度」を活用する/1ユニット終わったらシールを貼るとか、小さな達成感を演出すると、やる気が続く
ごほうびは「大きな報酬」よりも「小さな達成感」の積み重ねがカギ。
1ユニット完了ごとにシールを貼る、シートを埋める、スタンプカードにチェックを入れるなど、視覚的な報酬が効果的です。
これにより「今日はやった!」という充実感が得られ、モチベーションが維持されます。
特に低学年におすすめの方法です。
使い方3・親も一緒に楽しむ姿勢を/とくに低学年は、親が「一緒にやろう!」と言うと素直に取り組むことが多い
小学生はまだまだ親の存在が学習のモチベーションになります。
「一緒にやってみよう」「これ面白いね」といった声かけで、子どもは自然とやる気を出すことが多いです。
放っておくよりも、ほんの5分でも付き添うことで、集中度や学習の定着率がグッと上がる傾向があります。
親が前向きに取り組む姿勢を見せることが鍵です。
使い方4・苦手克服から入るのがおすすめ/好きな科目ばかりやると偏るから、すららのAI診断で弱点を把握して、そこから攻略する
得意教科だけを繰り返すと、どうしても偏りが出ます。
すららはAIが苦手を自動診断してくれるので、まずは苦手分野から取り組むのがおすすめ。
最初は抵抗があっても「わかった!」が1つでも増えると、やる気も伸びていきます。
特に算数や国語の基礎力は、低学年のうちに丁寧に積み上げておきたいポイントです。
【中学生】すららの効果的な使い方について紹介します
中学生になると、勉強が本格化し、部活との両立やテスト対策の重要性が増してきます。
すららをうまく使えば、「学校の授業+α」の学習が効率よくこなせるようになります。
特に中1・中2では「復習と予習のバランス」を取りながら、自主学習のリズムを確立するのがカギ。
また、中3生は内申点や受験対策を意識して使うと、得点力アップにも直結します。
すららの学習計画機能やAI診断をフル活用しながら、自分の目標に向けてスマートに活用していくと良いでしょう。
使い方1・「定期テスト対策」に直結させる/単元ごとにまとめテストがあるから、テスト範囲を逆算して、今どこをやるべきか計画を立てる
中学生にとって定期テストは成績・内申に直結する重要なイベントです。
すららでは単元ごとの確認テストが豊富に用意されているため、テスト範囲に合わせて学習を逆算し、ピンポイントで対策ができます。
復習→理解→定着までを効率よくまわせるのが最大の強みです。
テスト直前だけでなく、日々の積み重ねが成果に繋がります。
使い方2・部活後の「夜学習」を習慣に/寝る前の「タブレット学習ルーティン」を決めると、ペースが乱れない
部活や習い事で忙しい中学生には、短時間でも夜に「すららタイム」を作るのが効果的です。
帰宅後に夕食・入浴を済ませたあとに「すららを1単元だけやる」と決めておくことで、学習習慣が乱れにくくなります。
日々の学習が短時間でも積み重なることで、無理なく成績アップを狙えるスタイルが確立します。
使い方3・「すららコーチ」をフル活用/学習計画のアドバイスやつまずきのサポートをしてくれる
すららの最大の特徴のひとつが「すららコーチ」の存在です。
学習計画を子どもに合わせて設計してくれるだけでなく、つまずきのフォローや、学習姿勢へのアドバイスまでサポートしてくれます。
保護者が言いにくいこともコーチが言ってくれるため、第三者の立場からの声がけで子どもも前向きに学習しやすくなります。
使い方4・「復習と予習」をバランスよく/英語や数学の文法・公式の理解は予習でやると授業が楽しくなる
中学生の学習では「復習の定着」と「予習の準備」がセットで重要になります。
すららのAIは今の理解度をもとに、最適な単元を提示してくれるので、授業の前に触れておくだけで内容の理解度が高まります。
特に英語や数学は、予習で土台を固めておくことで、学校の授業が「復習の場」となり、成績向上につながりやすくなります。
【高校生】すららの効果的な使い方について紹介します
高校生になると、学習内容がより高度化し、定期テスト・模試・受験と明確な目標に向かって勉強する必要が出てきます。
その分「自分のペースで学べる」すららの柔軟性は大きな武器になります。
特に進度に差が出やすい数学や英語では、つまずきを放置すると致命的。
でもすららなら、苦手分野をAIがピックアップし、理解不足の箇所をさかのぼって補強できます。
また、共通テスト対策としても有効で、基礎を網羅したカリキュラムと定着確認テストがあるので「わかったつもり」を見逃さず、本質的な力を養えます。
自己管理が求められる高校生活において、「学習時間の見える化」「コーチとの定期チェック」など、自主的な学習習慣を支える機能も充実。
すららをうまく活用すれば、塾に頼らず自走力を育むことも可能です。
使い方1・「苦手克服」×「得意分野の強化」を並行する/つまずいてるところは基礎から復習し、得意分野は応用問題に挑戦する
高校生の学習では「バランスのとれた学習戦略」が重要です。
すららのAI診断は、苦手を自動検出し、基礎から丁寧に戻る学習が可能。
一方、得意な分野は応用問題へ進むことで、得点力アップにつながります。
苦手を残さず、得意を伸ばすこの「並行学習」は、受験においても大きな強みとなります。
使い方2・学校の授業が合わない場合は、すららで自分に合うペースで進める
学校の授業が速すぎる、あるいは遅すぎると感じる高校生も少なくありません。
そんなとき、すららの無学年式カリキュラムなら、自分に合ったスピードでの学習が可能です。
理解が浅い部分は何度でも繰り返し学べ、理解が深いところはスキップもできる。
「ムダなく学ぶ」を叶えてくれます。
使い方3・模試や共通テスト対策に連動/すららは基礎力の定着にはかなり強い
模試や共通テストに必要なのは「応用力の前に基礎力」です。
すららは、基礎をしっかりと固められる構成になっており、特に英語・数学・国語の基本構文・公式の理解に優れています。
苦手な分野が点として浮き上がるので、模試対策としても効率的です。
志望校別にピンポイント学習が可能になります。
使い方4・学習時間を「見える化」する/学習時間や達成度がグラフで表示される
高校生にとって「どれだけやったか」を可視化することは、モチベーション維持に直結します。
すららでは学習時間や単元達成度がグラフ化されて表示されるため、「今日はこれだけ頑張った」という実感が得られます。
計画→実行→振り返りというPDCAを回す癖を自然と身につけることができます。
【不登校】すららの効果的な使い方について紹介します
不登校の子どもにとって大切なのは、「無理せず、安心できる環境で学ぶこと」。
すららは、登校が難しい子でも自宅で学び続けられる仕組みが整っており、プレッシャーなく自分のペースで学習を進められる点が大きな魅力です。
さらに、すららは「出席扱い」として学校で認められるケースも多数あり、学習の遅れをカバーするだけでなく、内申点や進学の選択肢も広がるのがポイント。
生活リズムを整えるツールとしても活用でき、子どもの自己肯定感の回復にも一役買います。
特に保護者から「すららがあって助かった」と支持される理由は、親の負担を減らす「コーチの存在」や、「一人でも学べる安心感」にあります。
使い方1・「生活リズム作り」に役立てる/朝起きる→学習→休憩…の「ミニ時間割」を作って生活リズムを整えられる
不登校で昼夜逆転してしまった場合でも、すららの「生活の中に学習を組み込む」機能を活用すれば、少しずつリズムを戻すことが可能です。
朝起きたらまず10分のすらら、昼食前にもう1単元など、日常のルーティンに学習を取り入れることで、無理のない範囲で生活リズムが整っていきます。
使い方2・「一人でも安心してできる環境」を整える/自分のペースで、周りを気にせず学べるのがすららの強み
「学校のように集団の中で学ぶのが苦手…」という子にとって、すららは自室で静かに、かつ対話形式で学べる教材です。
先生や友達の目がない分、プレッシャーがなく、つまずいても何度もやり直せる。
安心できる環境で、誰にも見られずに自分だけの学びができることが、大きな安心材料になります。
使い方3・「成功体験」を増やして自信を回復/すららの「ほめ機能」を活用する
不登校の子どもは「できなかった自分」に対する自信喪失が大きな課題になります。
すららでは、正解するとキャラがほめてくれるなど、小さな成功体験を積みやすい設計になっています。
この積み重ねが「またやろう」「やってよかった」という前向きな気持ちを引き出し、自己肯定感の回復につながります。
使い方4・コーチングの活用で「孤立感」を減らす/すららコーチに相談すると、親とは違う「第三者の声」がもらえるので、気持ちの負担が和らぐ
親だけで子どもの不登校を支えるのは、どうしても限界があります。
すららの「すららコーチ」は、学習面だけでなく、子どもの気持ちにも寄り添ってくれる第三者的な存在。
親に言いにくいこともコーチには言えることが多く、学習への向き合い方が変わるきっかけになります。
孤立感の緩和にもつながる重要な支援です。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららを実際に利用したユーザーの評判を紹介します
良い口コミ1・うちの子は、元々タブレットが好きで、ゲーム感覚で学べるところがハマったみたいです。
アニメのキャラが優しく教えてくれるので、塾に行くよりも緊張しないし、自分のペースでできるのが良いみたい
良い口コミ2・ADHD気味で集中力が長続きしない子でも、すららはアニメーションやイラストで説明してくれるので理解しやすいです
良い口コミ3・学校に通えない期間が長く、勉強にブランクがありましたが、すららなら自分のレベルに合わせて無理なく進められました。
先生の顔を見ずに自分だけのペースで学べるので、安心感があります
良い口コミ4・塾に通う時間が取れなかったけど、すららは家でスキマ時間にできるから便利!部活が忙しくても、夜に少しずつ進めていけるし、テスト対策にも使えるのがいい
良い口コミ5・発達に凸凹があって、書くことが苦手な子ですが、すららはタブレット操作で進められるので、嫌がらずに学習ができています
悪い口コミ1・タブレットで勝手に学んでくれると思っていたけど、低学年の子は一人で進めるのが難しいこともあり、結局そばで見守ることに…。
もう少し親が楽できる設計だったらよかったかな
悪い口コミ2・初めは楽しく続けられていたのですが、不登校の子だと一度やる気が下がると放置してしまう…。
サポートメールや先生からのアドバイスは来るけど、やっぱり一人だと限界を感じることもあります
悪い口コミ3・高校生用のコースを受講していますが、基礎に時間をかけすぎる印象です。
進学校に通っていると、物足りなさを感じるかもしれません
悪い口コミ4・アニメーションで楽しく学べるのはいいけれど、うちの子は飽きるのも早くて…。
もう少し、変化に富んだコンテンツがあると良いですね
悪い口コミ5・通塾よりは安いですが、長期間利用を考えるとそれなりに負担感があります。
特に兄弟で同時に使う場合は、一人ずつの契約が必要なので、コストはやっぱりかさみます
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの会社概要を紹介します
「すらら」は、株式会社すららネットが提供する家庭用タブレット教材です。
この会社は2005年に設立され、長年にわたり「学びの個別最適化」をテーマに、無学年式のICT教材を開発してきました。
本社は東京都千代田区にあり、上場企業(東証グロース)としても信頼性があります。
特に、発達障害や不登校など、多様な子どもたちへの支援に力を入れており、文部科学省の認定教材としても活用されるなど、社会的信頼度の高い企業です。
また、自治体や学校とも多数連携しており、全国の教育委員会に導入実績があります。
すららネットの強みは、「AI×コーチング」のハイブリッドサポートにより、単なる教材にとどまらない「学習の伴走支援」を提供している点にあります。
| 運営会社 | 株式会社すららネット |
| 創業 | 2008(平成20)年8月29日 |
| 本社住所 | 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田7階 |
| 従業員数 | 正社員88人、契約社員5人 |
| 資本金 | 298,370千円 |
| 代表取締役 | 湯野川 孝彦 |
| すらら公式サイト | https://surala.co.jp/ |
| すららの講座一覧 | ・3教科(国・数・英)コース
・4教科(国・数・理・社)コース ・5教科(国・数・理・社)コース |
参照:会社概要(すらら公式サイト)
【すらら】はうざい!?についてのよくある質問
「すららがうざい」と検索されることもありますが、これは一部の利用者が感じた不満が原因です。
ただし、学習教材としての評価は高く、多くのご家庭で効果を実感されています。
以下に、よくある質問をQ&A形式でご紹介します。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららが「うざい」と言われる主な理由は、「サポートが熱心すぎる」「キャラクターが子どもっぽい」「AI学習の圧が強い」といった声からです。
例えば、すららコーチの連絡頻度が「ありがたい」反面、「自分で学びたい子」には少し過干渉と感じる場合も。
また、キャラクターのナビゲーションも、好みによって「テンポが合わない」と不満を感じるケースがあります。
ただし、これらは裏を返せば「丁寧なサポート」や「継続しやすい工夫」の証拠でもあります。
万人に完全に合う教材は存在しませんが、うざいと感じる原因を知った上で選ぶことで、満足度はぐっと高まります。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには「発達障害専用コース」というものはありませんが、発達障害や学習障害(LD)、ADHD、ASDの子どもにも対応した柔軟な設計になっており、追加料金もかからず利用できます。
料金体系は通常プランと同じで、教科数・継続コースの有無で金額が異なります。
また、個別サポートとして専属コーチがつき、子どもの特性に合わせた学習計画を提案してくれます。
そのため、発達に課題のある子にも「最適な学び方」ができる環境が整っています。
合理的配慮が追加料金なしで受けられる点が、多くの保護者に選ばれる理由です。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
はい、すららは「出席扱い」として認められることが多く、不登校の子どもにも安心して利用できる教材です。
文部科学省が出しているガイドラインに準拠しており、学習の記録(進捗レポート)を学校に提出することで、担任や校長の判断で「出席扱い」となることがあります。
また、必要に応じて医師の意見書を添えるなど、すらら側も保護者をサポートする体制が整っており、教育委員会との連携実績も豊富です。
継続的に学習できること、そして学習環境が学校と同等と認められることが、出席扱いの条件です。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは、入会金無料や月額割引が受けられる「キャンペーンコード」が発行されることがあります。
キャンペーンコードは、主に公式サイトからの資料請求や説明会参加、あるいは株主優待などで入手できます。
利用方法はとても簡単で、申し込み時に専用フォームへコードを入力するだけでOK。
適用される特典(入会金無料・月額割引など)はその時期によって異なるため、最新情報をすらら公式ページで確認するのがおすすめです。
なお、有効期限や対象コースに制限があることもあるので注意が必要です。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららの退会は、まず「解約」と「退会」の違いを理解することが大切です。
解約は毎月の利用料金を止める手続きで、学習データやアカウント情報は残ります。
一方、「退会」はデータごと完全に削除する手続きです。
解約は電話連絡で行い、すららコール(サポートセンター)へ申請します。
その後、退会を希望する場合は、メールやフォームで別途申請が必要です。
どちらも締切は毎月25日で、それを過ぎると翌月扱いになるため注意が必要です。
また、再入会時には入会金が再発生する可能性があるため、「休会」制度の利用も検討しましょう。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららでは、基本的に「入会金」と「毎月の受講料」以外の追加料金は発生しません。
タブレットなどの専用端末も必要なく、お手持ちのパソコンやタブレットで利用できるため、教材費や機材費などの隠れたコストがかかる心配もありません。
ただし、インターネット環境は自宅で用意する必要があり、Wi-Fiなどの通信費は各家庭で負担する形になります。
また、兄弟利用や複数教科の追加などによる料金体系の変動はありますが、それも事前に公式サイトや案内ページで明記されており、わかりやすい料金設計になっています。
学習アプリの中には、「途中から課金が発生する」ものも多いですが、すららは月額制の定額サービスなので、毎月の支払いだけを把握しておけばOKという安心感があります。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
はい、すららでは「1契約につき兄弟で一緒に使うことが可能」です。
追加料金なしで、兄弟・姉妹それぞれのアカウントを個別に作成でき、それぞれの進捗・学習履歴も個別に管理されます。
例えば、小学6年生のお兄ちゃんと中学1年生の妹が同じ契約内で学ぶというケースもOKです。
これは、他の教材にはない大きなメリットで、保護者からは「コスパが良すぎる」と評判です。
もちろん、すららコーチによるサポートもアカウントごとに提供されるので、子どもたちの特性や学年、学力レベルに合わせた個別フォローも安心。
兄弟で同時に申し込む場合には、入会金が2人目以降無料になるキャンペーンなどもあるので、事前にチェックしておくとさらにお得です。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生コースには「英語」も含まれています。
リーディング・リスニング・スピーキングの3技能に対応しており、ネイティブ音声による発音の聞き取り練習、音読のチェック、アニメーションを使った文法解説などが用意されています。
特に最近は「小学生から英語に触れておきたい」という保護者のニーズが高まっており、すららの英語教材はその声に応える内容になっています。
英検対策にも役立つ構成になっていて、単語・文法の学習だけでなく、実践的なフレーズの理解も可能。
発達段階や学年に関係なく、自分のペースで進められる「無学年式」なので、英語が苦手な子でもやり直しがしやすく、逆に得意な子はどんどん先に進めることができる柔軟な設計です。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららの「すららコーチ」は、ただの学習ナビゲーターではありません。
子どもの学習スタイルや生活リズム、特性を見極めながら、完全オーダーメイドの学習計画を作ってくれる伴走型サポーターです。
保護者にとっては「塾の先生と家庭教師を足したような存在」とも言われており、コーチからは定期的な進捗確認やアドバイスのメール連絡が届きます。
学習に関する質問や悩みにも直接相談でき、発達障害や不登校の子どもにも寄り添ったサポートが期待できます。
特に、つまずきやすい単元に差しかかると、事前に「ここは注意ポイント」とフォローをくれるので、子どもも安心して取り組めるのが大きな魅力。
親が毎日横で見ていなくても、自主的に学べるよう導いてくれるのがすららコーチの強みです。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材と比較しました
「すららはうざい」と言われる口コミがある一方で、他の家庭用タブレット教材と比べたとき、実は非常にバランスの取れたサービスだという意見も少なくありません。
Z会やスマイルゼミ、スタディサプリなどと比較すると、すららは「無学年式」「発達障害や不登校対応」「コーチによる個別サポート」という点で圧倒的に特化しているのが特徴です。
他教材は学年に沿ったカリキュラムが多い中、すららは子ども一人ひとりのペースに合わせて学習できるのが強み。
コーチのサポートが「しつこい」と感じる場合もありますが、それは裏を返せば「しっかり見てくれている証拠」。
他社にはないサポート体制があるからこそ、保護者からの評価も高いのです。
家庭ごとのニーズに応じて選ぶべき教材ですが、「うざい」と感じるか、「安心できる」と感じるかは使い方次第と言えるでしょう。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較まとめ
すららに対して「料金が高い」「サポートがうざい」という口コミが目立つ一方で、実際に使っている家庭からは「内容を考えれば納得の価格」「コーチの存在がありがたい」といった声も多く聞かれます。
月額料金は他のタブレット教材より若干高めに見えるかもしれませんが、兄弟で使える・無学年式で学年をまたいで学べる・発達障害や不登校対応が標準で含まれている点を考えると、むしろコスパは高いと言えるでしょう。
「最悪の噂」とされる部分の多くは、サポートの頻度やキャラクターの好み、AI診断による学習の自動調整などが合わなかったユーザーの声が中心です。
タブレット教材は相性がすべて。
すららが提供している価値が必要な家庭にとっては、これ以上にピッタリの教材はなかなか見つからないという評価もあるのが事実です。
