すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
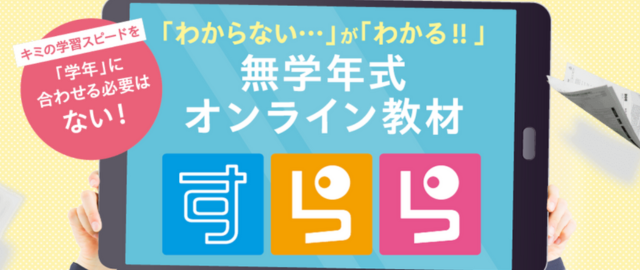
「すらら」は、不登校の子どもたちにも安心して学べるオンライン学習教材として、多くの家庭で支持を集めています。
特に注目すべきは、すららでの学習が「学校の出席扱い」として認定されるケースがあるという点。
これは、文部科学省が定めた「出席扱いの要件」に対応した設計と実績があるからです。
具体的には、学習の質と継続性が保証されていること、そして学習記録を提出できる仕組みが整っていることが理由です。
さらに、専任のコーチによる学習計画の作成や進捗管理も評価の対象となっており、ただ「勉強している」だけでなく「計画的・継続的な学習」として学校側にアピールできるのが特徴。
不登校の状態でも、安心して教育を受けられる環境として、すららは非常に信頼性が高い選択肢といえるでしょう。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
出席扱いの認定には、子どもが自宅で「教育的に適切な学習活動」を継続している証明が不可欠です。
すららはこの点で非常に優れており、学習内容・進捗・理解度などを自動的に可視化できる学習記録システムを搭載しています。
すららの学習履歴は、保護者のマイページからPDFとしてダウンロードでき、提出書類としてそのまま使用することも可能。
さらに、学校の担任や校長先生に提出するための「学習状況レポート」も、フォーマットとして整っているので安心です。
保護者が手作業で日誌を作る必要がなく、教育機関からも評価されやすい点が、多くの不登校支援に活用されている理由のひとつです。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららでの学習データは自動的に記録され、いつ、何を、どのくらいの時間学習したかが分かる形式でレポート化されます。
このレポートはPDF形式で出力でき、学校側へそのまま提出できるよう整備されているため、家庭での学習が第三者にとっても明確に「見える化」されているのが大きなポイントです。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
子どもの勉強をサポートしたくても、日々の忙しさで学習管理まで手が回らない…そんな保護者にとって、すららの自動記録機能は大きな助けになります。
保護者が手書きで記録を取る必要がないうえに、フォーマットも整っていて、学校側にとっても提出資料として信頼性が高く、スムーズな出席扱いの申請につながります。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
出席扱いが認定されるかどうかのカギは、「学習の継続性」と「個別最適化された計画」の存在です。
すららでは、子どもの学力や特性に合わせて、専任の「すららコーチ」が学習計画を立案してくれます。
無理なく続けられるスケジュールがあることで、子どもも安心して取り組むことができ、結果的に「計画性を持った継続学習」として評価されやすくなります。
また、つまずきがあった場合にはすぐに軌道修正ができるよう、コーチが都度フォローアップしてくれる点も、他の教材にはない大きな強みです。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
すららでは、毎週・毎月の学習目標を立て、それを継続して進めていく「学習計画サポート」がコーチによって行われます。
この記録はすべてデジタル上で確認可能で、学校への報告資料として使えるのが魅力。
コーチの存在があることで、学校側も家庭学習の信頼性を感じやすくなります。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
一人ひとりの理解度・学習スピードに応じて、コーチが個別に計画を立ててくれるため、子どもが無理なく学習を継続できます。
「今日はやる気がない」という日があっても、その後のフォローがあるため、ペースを乱さず継続できるのが特長。
継続性を証明しやすく、出席扱い申請時にも有利です。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
すららの学習は無学年式で、学年にとらわれず自由に「戻る・進む」が可能。
つまずいた単元に立ち返って学べるため、学力にギャップがある不登校の子にもピッタリ。
理解度に応じた柔軟な対応ができることで、学校の先生も「この子は本気で取り組んでいる」と受け入れてくれやすくなります。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
すららが「出席扱い」として認められやすい理由のひとつが、家庭・学校・すららの三者がしっかり連携できるサポート体制にあります。
すららでは、出席扱い申請に必要な書類の準備方法を、保護者向けに丁寧に案内してくれます。
さらに、学習進捗レポートの作成フォーマットがあらかじめ用意されているため、保護者が一から書類を作成する必要がありません。
また、すららの専任コーチは、学校とのやりとりにおけるアドバイスもしてくれるため、担任や校長先生との連携も取りやすくなります。
「家庭だけでは不安…」「学校にどう伝えていいかわからない…」という親御さんにとって、非常に頼もしいサポート体制が整っている点が、他の教材にはない大きな強みです。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
すららでは、学校へ提出する「学習記録レポート」や「出席扱い申請書類」の作り方について、マニュアル形式で案内がもらえます。
こうした細かなサポートがあるから、保護者が「何をどうすればいいの?」と悩まずに済むのです。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
提出すべき学習レポートは、すらら内で自動生成も可能ですし、コーチが確認・添削までしてくれます。
どの項目に何を書くべきか、どう書けば学校が納得するか、そういった実務的なアドバイスまでフォローしてくれます。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
学校とのやり取りに慣れていない保護者の方にとって、担任や校長との話し合いは緊張するもの。
すららでは、「こう伝えればスムーズ」など具体的なコミュニケーション方法の相談もできるので、心の負担がぐっと軽くなります。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、文部科学省のガイドラインに準拠した、不登校の児童・生徒向けのICT教材として広く認知されています。
実際に全国の教育委員会や多くの小中学校、高校でも導入されており、公的機関との信頼関係も強固です。
特に、不登校児童生徒に対して「ICTによる自宅学習が出席扱いになる」制度において、すららはその実績と信頼性から多くの採用事例をもっています。
このように国や教育現場からの評価を受けているからこそ、保護者も安心して導入できるのです。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは全国の公立・私立の教育機関との導入実績があり、教育委員会とも連携してきた実績を持ちます。
この実績があるからこそ、出席扱いの申請も前例としてスムーズに進むケースが多いです。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは、公式に「不登校支援教材」として認定され、各自治体の案内にも記載されることがあります。
文部科学省のガイドラインに則った設計で、教育現場からも信頼されている点は、教材選びの安心材料になるでしょう。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
すららは、学習指導要領に沿ったカリキュラムで構成されており、学校教育と同等の内容を家庭でも学べるようになっています。
さらに、AIとコーチのサポートにより、「評価・フィードバックの仕組み」まで完備されているため、学校側からも「学校に準じた学習環境」として認定されやすい特徴があります。
単なる自習教材ではなく、「指導計画に基づく継続学習ツール」として信頼されているのです。
不登校でも出席扱いになるための大前提である“学習の質と量の保証”をしっかり満たしている点が、多くの家庭から選ばれる理由のひとつです。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららの教材は、学年ごと・科目ごとに文部科学省の指導要領に沿った内容で構成されており、学校の授業と整合性があります。
そのため、学校側からも「正式な学習」として受け入れられやすいのです。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
学習の到達度や進捗状況は、すららのシステム内で自動的に記録・可視化されます。
また、定期的なチェックテストやコーチからのフィードバックによって「評価の仕組み」も機能しており、学校からも教育の継続性が認められやすい設計になっています。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
すららは、不登校の子どもでも「出席扱い」として学校に認められる可能性がある、数少ない家庭学習教材の一つです。
文部科学省のガイドラインでは、「ICTを活用した自宅学習」が一定の条件を満たしていれば、出席とみなされる制度があり、すららはその対象に適した教材として多くの導入実績を持っています。
ただし、出席扱いになるには学校や教育委員会との連携が不可欠で、申請にはいくつかのステップを丁寧に踏む必要があります。
ここでは、すららを使って出席扱いにしてもらうための具体的な申請方法をわかりやすく解説していきます。
学校との信頼関係を築きつつ、子どもが学びを継続できるよう、親御さんができる準備や対応を知っておきましょう。
申請方法1・担任・学校に相談する
出席扱いを希望する場合、まず最初にすべきなのは担任や学校に相談することです。
いきなり書類を出すのではなく、事前に「すららという教材を使って家庭学習をしていること」「継続して取り組んでいること」を学校に説明し、出席扱い制度について協力をお願いしましょう。
多くの学校では、校長の裁量で出席認定の判断を行うため、学校側との信頼関係づくりが重要です。
また、学校によっては、独自の書式や提出期限がある場合もあるので、早めに条件や必要書類を確認しておくと安心です。
すららの公式資料などを印刷して一緒に提出すると、教育効果の説明もしやすくなります。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
出席扱い申請に必要な書類は学校によって異なりますが、一般的には「学習記録」「家庭学習計画書」「教材の説明資料」などが求められます。
担任の先生や学校の指示に従い、必要なフォーマットがあれば事前に入手し、正確に記入して準備しましょう。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
不登校の原因が「病気」や「精神的な理由」によるものである場合、学校によっては医師の診断書や意見書が必要になることがあります。
たとえば、発達障害や適応障害、情緒不安定などが背景にある場合、それを医学的に証明することで、学校も安心して出席扱いを認めやすくなります。
診断書には「現在の状態」や「家庭での学習継続が望ましいこと」が記載されていることが理想的です。
主治医には事情を詳しく説明し、必要な情報を書いてもらえるよう相談しましょう。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
学校によっては「家庭学習が妥当かどうか」を判断するため、医師の意見が求められます。
すべてのケースで必要なわけではありませんが、心の不調や障害の診断がある場合は診断書があるとスムーズです。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書には「出席扱いを望む家庭学習が継続的に行われていること」「今後も必要であること」が明記されていると、学校側が判断しやすくなります。
医師との信頼関係を活かして、正確に事情を伝えることが大切です。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
すららには「学習記録レポート」が自動で出力できる機能があります。
このレポートには、教科ごとの学習時間、進捗、テスト結果などが記録されており、学校に対して「しっかり学習している証拠」として提出できます。
また、担任や校長先生に提出するための書類として、保護者が協力して記入する「出席扱い申請書」も必要になることがあります。
これらをセットで提出することで、出席扱いが認められる可能性がぐっと高まります。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららのマイページからダウンロードできるレポートには、日々の学習履歴や学習の到達度がまとめられており、視覚的にもわかりやすく整理されています。
これが提出資料の信頼度を高めてくれます。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
申請書は学校側で準備される場合が多いですが、必要な情報(家庭学習の方法、学習時間、教材内容など)は保護者が正確に伝える必要があります。
すららのコーチに相談しながら作成すると安心です。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
最終的に出席扱いになるかどうかは、学校長または教育委員会の判断に委ねられます。
学校によっては校長判断だけで完結することもあれば、教育委員会に申請が必要な場合もあります。
申請が通るかどうかは、書類の正確さ・継続的な学習の実績・学校との連携の取り方が大きく影響します。
保護者としては焦らず丁寧に手続きを行い、学校側とこまめに連絡を取り合うことが大切です。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
多くのケースでは、校長先生の裁量で最終的な判断が下されます。
学習内容の妥当性、家庭の支援体制、学習記録の信頼性などを総合的に判断されます。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
一部の自治体では、教育委員会への正式な申請が必要なケースがあります。
保護者だけで対応せず、学校側に確認しながら一緒に書類を作成して提出しましょう。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
不登校のお子さんにとって、「すらら」を使って出席扱いとして認定されることには多くのメリットがあります。
単に学習が進むだけではなく、将来に関わる「内申点」や「進学の選択肢」にまで影響を与えるのが大きなポイントです。
さらに、学習を継続することで「遅れている」「取り戻せない」という焦りや不安が軽減され、子どもの自信にもつながります。
そして見逃せないのが、親の心の負担が大きく減るという点。
不登校の子どもを支える家庭では、精神的にも体力的にも限界を感じる場面が多いものです。
すららを活用することで、家庭・学校・学習コーチという「三位一体のサポート体制」が整い、保護者も「ひとりで抱え込まなくていい」と感じられるはずです。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
出席日数が足りないと、どんなにテストの点数が良くても内申点が大きく下がるリスクがあります。
特に中学生にとって、内申点は高校進学の合否に直結する重要な評価指標です。
「出席扱い」として認められれば、欠席とみなされないため、内申点への悪影響を最小限に抑えることができます。
また、学び続けている実績が明確になるので、進学面談でも安心感を持って話を進められるようになります。
将来の選択肢が狭まらないようにするためにも、すららを活用した出席扱いの申請は有効な手段といえるでしょう。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
出席日数の不足は、成績以上に内申点に影響を及ぼします。
すららで出席扱いになれば、このリスクを回避できます。
学力だけでなく、出席状況が整うことで評価も安定します。
中学・高校進学の選択肢が広がる
内申点をキープできれば、志望校の幅も広がります。
不登校でも「学習を継続している」という証明ができれば、公立・私立問わず選択肢を狭めずに進学を目指せます。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校になった子どもたちが抱える不安の多くは、「クラスの友達に比べて遅れている」「もう取り返せないのでは」という自己否定感です。
すららを使えば、無学年式で自由に学習を進められるため、焦らず確実に力をつけていくことができます。
また、AIによる苦手分析や自動レコメンド機能があるため、何をどう勉強すればいいかが明確になり、効率的に学べる環境が整います。
こうした積み重ねが、自然と「できた!」という成功体験に変わり、勉強に対する抵抗感を減らしていきます。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
すららは、カリキュラムを自分のペースで進められる設計です。
わからないまま先に進むことがないので、復習しながら安心して取り組めます。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
学習の継続は、自信の回復にもつながります。
小さな達成が積み重なって「自分はできる」という実感が持てるようになると、再び学校とつながるきっかけにもなります。
メリット3・親の心の負担が減る
子どもが不登校になると、親は学習のことだけでなく、心のケアや将来の不安、学校との対応など、多くのことを1人で抱えることになります。
すららには「すららコーチ」という専門スタッフがつき、学習計画の作成から進捗確認、モチベーション管理まで丁寧にサポートしてくれます。
このサポートにより、保護者が毎日つきっきりで見守る必要がなくなり、精神的な余裕も生まれます。
学校との連携書類などもコーチがフォローしてくれるため、「どう進めればいいか分からない」という迷いもなくなります。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららを通じて、家庭・学校・学習サポートが連携しやすくなります。
保護者が孤独を感じることなく、安心して学習環境を整えられるのは大きなメリットです。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
すららを使って不登校でも「出席扱い」にしてもらうためには、いくつか注意すべきポイントがあります。
ただ単に学習しているだけでは学校側に認定してもらえないこともあるため、手続きや提出書類、そして学校との連携がとても重要です。
特に、すららは文部科学省のガイドラインにもとづいた教材であることを学校側に理解してもらう必要があります。
教師や校長との信頼関係づくり、医師からの診断書の取得、学習記録の提出など、細かい手順を踏まえて申請することで、出席扱いとして認められやすくなります。
ここでは、すららで出席扱いを目指す際に保護者が知っておくべき「注意点」を具体的に紹介していきます。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
すららを使った出席扱い制度は、あくまで学校長の判断で認定される制度です。
つまり、最終的には担任や教頭、校長の理解と協力が欠かせません。
そこで重要なのが、すららが「文部科学省の定める出席扱いの条件に準拠している教材である」という点を丁寧に説明することです。
すららの公式資料や、出席扱いに関するパンフレットなどを持参して、視覚的にも信頼性を伝えるようにすると効果的です。
担任の先生だけでなく、場合によっては学年主任や教頭、校長にも直接話を通す必要があることもあるため、できるだけ早めにアプローチを開始しておくのがおすすめです。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
出席扱い制度には文科省のガイドラインが存在します。
すららはこの条件に対応している教材ですが、学校側が知らない場合もあります。
保護者の口から説明し、信頼性を伝えることが大切です。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
実際の申請時に効果的なのが、すらら公式の出席扱いガイドやパンフレットを持参すること。
目に見える資料があると説得力が増します。
また、担任に任せきりにせず、早めに管理職にも相談を入れておくことで、スムーズに進めやすくなります。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
出席扱いの申請においては、不登校の背景によって医師の診断書や意見書の提出が求められることがあります。
特に、精神的な理由や体調不良が原因で学校に通えない場合、その状況を客観的に証明するために診断書が必要とされるケースが多いです。
小児科や心療内科を受診して、「家庭学習が継続されており、出席扱いが望ましい」旨の文言を書いてもらえるようお願いすることが重要です。
そのためには、医師に対しても、家庭での学習内容や子どもの意欲を具体的に説明しておくと良いでしょう。
医師も記載内容に困らず、協力しやすくなります。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
医師の意見書は、「不登校の正当な理由がある」という証明になります。
これは学校や教育委員会が出席扱いを認定する際の重要な材料になりますので、用意しておくと安心です。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
診断書が必要な場合は、単に「不登校」であることではなく、「家庭学習の継続が望ましい」「出席扱いが妥当」といった文言を記載してもらえるよう、しっかり依頼しましょう。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
医師も状況を把握しないと書類作成に苦労します。
すららでどのくらい学習しているか、どのように取り組んでいるかを保護者から説明することで、より具体的で有効な診断書を作ってもらえる可能性が高くなります。
注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
すららを使った家庭学習が出席扱いと認められるためには、内容や時間が「学校の授業に準ずるレベル」であることが前提になります。
つまり、ただ自宅で参考書を読んでいるような自習だけでは不十分。
すららのように学習指導要領に対応した教材で、系統立てた学習が必要です。
特に、1日2~3時間程度の学習時間を確保することが推奨されており、学習履歴としてしっかり可視化できることも重要なポイント。
また、国語・算数(数学)・理科・社会・英語といった主要教科をバランスよく進める必要があります。
たとえば、得意な英語ばかりを進めていては出席扱いの対象外となる可能性もあるため、全体の学習計画を意識して取り組むことが大切です。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
家庭での勉強が出席扱いとされるには、学習指導要領に準じた内容が必要不可欠です。
学校の授業に近い内容をすららでこなしているかを意識して、家庭学習の質を高めましょう。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
出席扱いにされるかどうかは「時間の確保」も大きな基準です。
理想は1日2~3時間程度。
朝・昼・夕とわけて短時間集中でもOKです。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
英語や数学だけではなく、理科や社会も含めた全教科を学ぶことが求められます。
苦手科目もまんべんなく取り組むことで、学校側の評価も得やすくなります。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いのもう一つの重要な条件が「家庭と学校との定期的な連携」です。
いくらすららでしっかり学習していても、それを学校が把握できなければ意味がありません。
月に1回を目安に学習レポートを担任や校長に提出することで、「継続して学んでいる」ことを証明できます。
すららではレポートを簡単にダウンロードできる機能があるため、活用しましょう。
また、学校側が希望する場合は、家庭訪問やオンライン面談にも柔軟に対応する姿勢が求められます。
担任の先生とは定期的にメールや電話でやり取りし、学習状況や変化を共有することが、信頼関係を築くカギになります。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
学校と家庭が連携してこそ出席扱いが実現します。
どれだけ学習していても、学校にその事実が届いていなければ意味がありません。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららには学習進捗レポートのダウンロード機能があります。
これを毎月提出すれば、学校側の理解と信頼が得られやすくなります。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学校側は、学習環境や本人の様子を把握したいと考えます。
家庭訪問や面談は、出席扱いに向けた大事なアピールの場にもなります。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
日々の小さな変化も、担任に伝えておくことで、出席扱いの条件を満たしやすくなります。
信頼関係をコツコツ積み上げましょう。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
学校によっては、出席扱いの申請を教育委員会を通じて行う必要があるケースもあります。
特に市区町村によって規定や対応が異なるため、担任や校長先生と相談しながら進めることが肝心です。
教育委員会への申請が必要な場合、学習記録や医師の診断書に加えて、学校からの推薦状が求められることもあります。
こうした書類の準備は一人では大変ですが、すららには保護者向けのサポートもあるので、遠慮なく相談しましょう。
大切なのは、「制度を理解してもらい、信頼してもらう」ことです。
焦らず、丁寧に進めれば、出席扱いの実現は可能です。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会への申請は学校と一緒に動くのが基本。
どんな書類が必要か、いつまでに出すかを事前に打ち合わせしておくと安心です。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
すららを使って「出席扱い」を実現するには、学校や教育委員会への適切な働きかけが必要です。
学習内容が指導要領に準じていることは大前提として、学習の継続性や本人の意欲、さらには家庭と学校の信頼関係が重視されます。
特に不登校の子どもの場合、学習はできていても「学校に戻る気があるのか?」「社会性は大丈夫なのか?」といった目線で見られることもあるため、単に教材を使っているだけでは足りません。
そこで大切になるのが、学校側に「この子は継続して学んでいて、前向きに頑張っている」という確かな証拠を届けること。
今回は、すららを使って出席扱いを認めてもらいやすくするための「成功ポイント」をご紹介します。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
「出席扱い」として認められるかどうかは、学校側の判断に委ねられる部分が大きいです。
そこで効果的なのが、すでにすららを導入して「出席扱い」になった学校の事例を提示すること。
すららの公式サイトには、全国の学校での採用実績や事例が豊富に掲載されているため、それをプリントアウトして担任や校長先生に見せるのが◎。
前例を示すことで、「この方法なら安心だ」と学校側も判断しやすくなります。
また、学校が教育委員会へ提出する際にも「他の学校でも認められている」という事実が強力な説得材料になります。
主張ではなく“実績”でアプローチすることで、通りやすさがグッと変わってきます。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
実際の事例を提示することで、学校側の警戒感を和らげることができます。
具体的な学校名や地域がわかると、より信頼性が増します。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
公式ページには出席扱いの成功例が掲載されています。
URLを送るだけでなく、印刷して資料化することで先生方も確認しやすくなります。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
学習の継続はもちろん重要ですが、それ以上に大切なのが「本人の意思」です。
どれだけ優秀な教材を使っていても、「親にやらされているだけ」「本人の意欲がない」と判断されてしまっては出席扱いが認められにくくなります。
そこでおすすめなのが、本人に簡単な学習日記や目標シートを書いてもらうこと。
短くても構いません。
「英語の発音が少しわかるようになった」「理科のクイズが楽しかった」など、本人の声は何よりも説得力があります。
また、学校との面談の際にはできるだけ本人も同席し、「がんばっている姿勢」を見せることができれば、大きなプラスになります。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
「がんばってる姿」は、紙一枚でも伝わります。
文章が短くても、自分の気持ちを表現することが最大のアピールです。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
少しの言葉でも構いません。
本人の表情や声が、学校側の印象を大きく左右します。
保護者だけでなく、ぜひ本人も同席を。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
どんなに良い教材を使っていても、学習が続かなければ出席扱いにはなりません。
重要なのは「続けられるかどうか」。
そのため、学習計画は本人のペースや体調に配慮しながら設計することが何よりも大切です。
すららには専任コーチがいるので、「この子にとって最適な時間・内容・順序」でプランを作ってもらえます。
例えば、朝10分からスタートし、午後は好きな教科に取り組む…など、柔軟で無理のないプランがポイントです。
継続できる習慣ができていると、学習レポートにも反映され、学校側の評価も高まります。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
「週に何日」「1日何分」というルールは、自分で無理なく守れる範囲にすることが大切。
無理は続きません。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
学習の専門家であるすららコーチなら、発達特性や生活リズムを考慮して、最適な学習設計をしてくれます。
ポイント4・:「すららコーチ」をフル活用する
すららの最大の強みのひとつが「すららコーチ」の存在です。
保護者が一人で抱え込まずに済むよう、学習のサポートはもちろん、出席扱いに必要なレポートや進捗管理、学校への提出資料の準備まで幅広くフォローしてくれます。
例えば、「月1回の学習レポートの提出が必要」となった場合、コーチが作成やダウンロードの手順まで教えてくれます。
また、学習が停滞しているときも「どう声をかけたら良いか?」など、保護者向けの相談も受けてくれるので安心です。
学校との信頼関係を築くためにも、コーチの存在は積極的に活用しましょう。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
すららコーチは「教材の先生」だけでなく、「制度のナビゲーター」でもあります。
書類関連のサポートも心強い味方です。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。
でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。
時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。
イライラして何度も怒ってしまっていましたが、
すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。
完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。
タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。
キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。
教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。
他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
不登校になってしまったお子さんを抱えるご家庭にとって、「出席扱いになるかどうか」は大きな問題ですよね。
文部科学省のガイドラインにより、一定条件を満たせば「家庭学習」でも出席として認定される可能性があります。
すららはこの条件をしっかり満たしており、出席扱いになった実績も多数。
とはいえ、初めて聞く保護者の方にとっては不安も多いはず。
ここでは、すららを使った出席扱い制度やよくある質問、制度の具体的な手順、注意点、そして実際に認められるための成功ポイントなどについてまとめました。
不登校でも学びを止めず、未来に繋げたいと考えている方にとって、有益な情報をお届けします。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
「すらら うざい」と検索されることがありますが、その背景には主に2つの理由があります。
1つは、すららのコーチングサポートが丁寧すぎて、連絡が多いと感じる方がいること。
もう1つは、学習時のナビゲーションキャラクターが低学年向けのデザインであるため、高学年や思春期のお子さんが「幼稚」と感じてしまうケースです。
しかし、これは裏を返せば、サポートが手厚く、キャラクターも飽きさせない工夫がされている証拠。
お子さまの性格や年齢に合わせて、どこまで活用するかを調整すれば、「うざい」どころか心強い味方になってくれる教材です。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには、明確に「発達障害専用のコース」は存在しません。
ただし、学習障害やADHD、ASDなどに配慮した設計がされており、通常コース内で無理なく取り組めるよう工夫されています。
料金に関しても、障害の有無や療育手帳の有無で料金が変わることはなく、すべての子どもに対して“フラットな教育機会”を提供する方針が貫かれています。
月額料金はコースによって異なりますが、兄弟での併用や長期割引など、お得に利用できる選択肢もあります。
サポート体制も充実しており、コーチが個別に対応してくれるので安心です。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
はい、すららは文部科学省の定めるガイドラインに基づき、不登校の子どもでも「出席扱い」になる条件を満たす教材として利用されています。
出席扱いを得るには、学習計画の明確さ、進捗状況の記録、継続性などが求められますが、すららはそのすべてに対応。
専任コーチが付き、学習レポートの提出や学習証明書の発行サポートもあるため、保護者の負担も軽減されます。
多くの自治体や学校での実績があり、安心して自宅で学びを継続できる教材です。
不登校でも「勉強を止めたくない」「将来の進学を見据えて出席を確保したい」と考える家庭には、非常におすすめです。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららのキャンペーンコードを使うことで、入会金が無料になったり、月額料金が割引されたりするお得な特典が受けられます。
入手方法としては、公式サイトで資料請求した後のオンライン説明会参加、株主優待によるコード提供などがあり、どれも無料で利用可能です。
実際にキャンペーンコードを使う際は、すららのマイページ上で登録時にコードを入力するだけで簡単。
コードには有効期限や適用コースの制限があることもあるので、事前に確認をしておくと安心です。
期間限定のキャンペーンなどもあるため、最新情報をチェックしながら活用してみてください。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららの退会には「解約」と「退会」の2つのステップがあります。
まずはサポートセンターへの電話で「解約」手続きを行い、毎月の料金をストップします。
その後、希望すれば「退会手続き」を別途申請することで、アカウント情報や学習履歴の完全削除が可能になります。
退会をするとすべてのデータが消えるため、再開する予定がある場合は「解約のみ」にしておくのがおすすめです。
なお、月途中で解約しても料金は日割りされません。
また、毎月25日までに解約をしないと、翌月の請求が発生する点にも注意が必要です。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららの料金体系は非常にシンプルで、基本的には「入会金」と「毎月の受講料」だけで利用できます。
教材費やサポート料などの追加料金は一切不要です。
タブレット端末も自前で準備できるため、レンタルや購入の義務もありません。
ただし、キャンペーンや特典によっては入会金が無料になることもあります。
また、プリント学習を併用したい場合などは自宅のプリンターや紙代などの実費がかかる程度です。
課金要素の多い学習アプリや教材とは違い、シンプルで継続しやすい点がすららの魅力のひとつ。
家計に優しく、安心して長期的に利用できる教材といえるでしょう。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららの嬉しい特徴のひとつが、「1契約で兄弟も利用できる」という柔軟さです。
すららでは同一アカウント内で、兄弟それぞれに個別のID(学習履歴付き)を作成することが可能。
たとえば、小学生のお兄ちゃんと中学生の妹が同じ契約内で学ぶこともOKなんです。
追加料金も基本的にはかかりません(※一部例外あり)。
学年に縛られない“無学年式”の教材だからこそ、兄弟でレベルや進度に合わせて学べる仕組みになっています。
「兄弟の学習費を抑えたい」「一緒にタブレット学習を始めたい」というご家庭にはとてもおすすめのスタイルです。
コスパ良く、家族みんなで学べる教材として人気です。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生コースには英語の科目も含まれており、学年に関係なく無理なく取り組める設計になっています。
英語が初めての子どもでも、「アルファベットの書き方」や「発音の練習」など基礎から丁寧に学べる構成です。
音声教材やアニメーションも豊富で、視覚・聴覚の両方を使った“多感覚学習”ができるため、苦手意識を持ちにくいのが特長。
さらに、リスニングだけでなく、スピーキング練習ができる音読チェック機能も搭載されています。
早期英語教育や英検準備を考えている小学生のご家庭にもぴったりな内容になっています。
子どもが「楽しい」と思える工夫がされているので、英語を自然に好きになってくれる子も多いですよ。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららの最大の魅力のひとつが「すららコーチ」の存在です。
このコーチは、ただのカスタマーサポートではなく、教育のプロとして子ども一人ひとりに合わせた学習設計・進捗管理をしてくれます。
最初にカウンセリングを行い、子どもの得意・不得意を分析したうえで、無理なく続けられる学習プランを提案。
さらに、週ごとの学習の進み具合を確認して、つまずいているところがあればすぐにサポート。
保護者にも定期的に学習レポートが届くため、安心して任せることができます。
また、発達障害や不登校のお子さんへの理解も深く、「第三者の専門的なサポート」があることで、親の負担もグッと軽減されます。
まさに、家庭と子どもをつなぐ“伴走者”のような存在です。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
すららは、不登校の子どもたちにとって「出席扱い」が可能な数少ない家庭用タブレット教材です。
文部科学省の出席認定ガイドラインに準拠した設計と、学校との連携体制が整っている点で他の教材と大きく異なります。
例えば、スタディサプリやスマイルゼミは個人学習に特化しており、学習内容は豊富でも「出席扱い」のためのレポート提出やコーチの介入サポートなどが限定的。
対してすららは、専任コーチが進捗管理やレポート作成をサポートし、担任や校長への説明資料まで提供してくれます。
さらに、学習ログは自動で可視化され、学校や教育委員会への提出もスムーズ。
実際に「すららで出席扱いになった事例」も多く紹介されており、不登校の家庭からの信頼も厚いです。
学力定着と制度対応の両面で優れている教材を探しているなら、すららは最有力候補です。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ
すららは、文部科学省の「出席扱いに関するガイドライン」に基づき、不登校の児童・生徒でも自宅学習を通じて“出席扱い”を受けることが可能です。
ただし、制度を正しく活用するには申請の手順を理解しておく必要があります。
まず、保護者が担任や校長先生に相談し、出席扱いの意向を伝えることが第一歩。
次に、すららでの学習状況を記録した「学習進捗レポート」や「学習時間の記録」を学校側に提出します。
必要に応じて、医師の診断書や意見書が求められる場合もあります。
その後、校長先生の判断や教育委員会の承認を経て、出席扱いが正式に認められます。
ただし、月末締切やレポートの提出漏れなど、細かい条件を満たす必要があるため注意が必要です。
すららは、これらのプロセスをスムーズに進めるための資料提供やコーチのサポートがあるため、他の学習サービスに比べて安心感があります。
出席扱いを目指すご家庭には特におすすめです。
